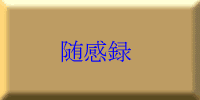 |
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2001年 2005年 2009年 2013年 2002年 2006年 2010年 2014年 2003年 2007年 2011年 2016年 2004年 2008年 2012年 |
30日に、みずほ総研から依頼の講演をして、そのまま西へ。そして、今日6月3日夜に帰ってきて、その間あったことなどをここに書きたいと思っていたのだが、その前に留守中に届いていた雑誌のインタビュー記事の内容の杜撰さに呆れて、旅行中のことを書く気が失せてしまっているうち、何日も経ってしまった。
先日もある雑誌のインタビュー記事に愕然としたが、今回も、一体このライターはこれでギャラを貰うのか、と呆れてしまう。もう散々このような目に遭っているので、これからはインタビュー等を希望される媒体は、私がすでによく知っている方をライターとして依頼するか、私に直接原稿を依頼されるか、いずれかにして頂きたい。
現に昨日は2件依頼があったが、事情をお話しして、かねて私がライターとして信頼しているT氏に2件とも引き受けて頂いた。ただT氏も忙しいので、いつもという訳にもいかない。そういう場合は私になぜ取材をしたいのか、その理由を400字以上の依頼文にして申し込んで頂きたい。
昨年9月にみずほ総研の『フォーレ』誌の依頼を受けたのは編集とライターを兼ねたK女史の、何年ぶりかに見るような見事な依頼文に心を動かされたからである。その依頼文に違わずK女史はきわめて優秀な方だった。その経験があるので、せめて依頼文を書いて頂きたいと思いついた訳である。このようなことを言うのは、何か思い上がっているようにとられかねないが、プロのライターの原稿に8割も赤入れをしなければならないのは、やはり異常事態というしかない。今の私は、そうでもしてこれ以上のストレスのかからぬようにするしかなく、この事に関して、今後依頼される方に心からお願いする次第である。
それにしても不思議なのは、まったくの素人で数千字の原稿に私が赤入れするところが20字もないような原稿をまとめられる人がいる事である。もちろん昔は、プロ中のプロは凄い人がいた。名著『逝きし世の面影』の著者で、間もなく刊行される『中央公論』誌で私との往復書簡が載る予定の渡辺京二先生は、かつて、かの吉本隆明翁にインタビューして、吉本翁に「一字も直すところがありません」と言わしめたらしい。そういう文章の達人が殆ど絶滅に近い状態になって、この後こうした達人の種の再生はなるのだろうか。トキやコウノトリの復活も応援したいが、私としては、ちゃんと人の話が聞けて、それを上手に文章にまとめられる人が今後絶えることなく育ってくれることを本当に心から望みたい。
以上1日分/掲載日 平成19年6月7日(木)
7日は何年ぶりかで加藤晴之氏に会い、やはり何年ぶりかで加藤氏の蕎麦を口にする。今から16〜7年前、初めて加藤氏の蕎麦を食べた時、「これが蕎麦なら、いままで食べていた蕎麦は一体何だったんだろう」と思った時の記憶が蘇ってくる。とにかく「美味い」とか「まずい」というよりも、何故か勝手に手が動いて食べてしまうのである。あの当時に比べれば蕎麦自体の力が落ち、その分作る技術を嫌でも磨かざるを得ないそうだが、一般の蕎麦との問答無用のレベルの違いはさすがである。
加藤氏の蕎麦を味わった後は、野口裕之先生の指導を受けるため身体教育研究所へ。先月、私の右上腕の1年半にもわたる痛みが、高校生の時、右人さし指の先をマムシに噛まれた事が原因であったらしいことが分かったのだが、今回野口裕之先生の内観はピンポイントで、それを捉えることに成功したようだった。「これが上手くつかまるかどうかは多分に運もあるんですけどね」との事だが(一体それがどういう感覚なのか、私には予想もつかないが)、それがピタリと捉えられたらしいことだけは嫌でも分かった。というのも、「ああ、分かったらしいなぁ」と私が思ってからしばらくの間、野口先生の手は私の腹部と肩にただ添えられるように当てられているだけなのだが、上腕部の痛みの凄まじいことといったらなかった。
この上腕部の痛みは、最近ではかなり良くなってきていて、手を上げる角度によってはまだまだ痛むが、何もしないでいれば、ほとんど気になることはない。ところが、この時の痛みは私がいままで58年間生きてきて、一度も体験したことのない、何というか百花繚乱の痛みのオンパレードなのである。痛みの表現に百花繚乱などというのは如何にもおかしいが、まるで夏の夜の打ち上げ花火のように様々な種類の痛みが立て続けに上腕部を襲ったのである。ある痛みは皮膚の下を龍が這うようにうねり、またある痛みは肘と肩の両端が逆方向に回転して骨を絞り上げるような力をかけるかと思えば、同じくその骨の中を稲妻が走りぬけるように。かと思うと、まるで巨大な磁石に引かれて鉄片が動くのに抵抗しているようなジーンとした痺れを伴った痛み。かと思うと、滝に打たれているような圧力を感じる痛み、あるいは水面に平たい石を投げると水の上を4回か5回跳ねて飛んで行くような痛みの断片が上から下へと点々と下がり落ちていく痛み。その痛みの表現があまりにも多彩だったせいか、私を観て下さっている野口先生が吹き出してしまわれたほどである。
私も長年整体協会の整体操法などの個人指導、個別稽古を見てきたが、整体指導者が指導中に吹き出して笑いがとまらなくなるなどという例は見たことがない。まあ、それほど私の言い方が感動のあまりおかしかったのだろう。 しかし、整体指導(というより野口裕之先生の技術)に理解のない人がこんな事になったら(そういう状況はあり得ないが)仰天して救急車を呼ぶだろうと思うほど、まったく理解の出来ない激痛が、いわばゾーンに入った野口先生の内観と同時に発生し、野口先生が指導を終えられても、しばらくは私は立つことも出来なかった。もちろん、その痛みはやがて潮が引くようになくなり、15分ほど後は普段の状態に戻った。
それにしても数十年というスパンで身体が記憶している身体の異常を呼び覚まし、本質的に体を整えるというこの技術は、科学という一対一対応の方法論では捉えようにも手がかりすら得ることは難しいだろう。しかし、どうやらある法則はあるらしい。ただ、それは同時にいくつもの要素が複雑に絡み合っている上、感覚をもって(といっても視覚や聴覚といった分かりやすい感覚ではない感覚)探究していくのだから、ますます科学の手には負えないだろう。 しかし、すぐれた音楽や絵画が科学の手には負えないという理由で拒絶されることがないならば、身体という本来その存在が快・不快という感覚で成り立っているものに対して、感覚による調律調整法があって当然だと思う。それが非科学的という一見もっともらしい理由で軽視されるという理不尽さは、近代がもたらした人類の不幸の一つの象徴であると思う。
10日に発売予定の『中央公論』7月号に載る私と渡辺京二先生の往復書簡"「逝きし世」に見る現代日本の失いしもの"の最後に、渡辺先生が現代の世相について「人間のために良かれと思ってしたことの積り積もった結果がこの有様です。どこで間違えたのでしょう。甲野さん、これがわれわれが今後考え詰めなければならぬ大きな問題ではないでしょうか」と結びの言葉を書かれているが、こと生命・健康に関して人間の感覚による、そのことへの関与を迷信として拒絶排除することを以て文明人の証しとするが如き暴挙が近代以後行われ、現在も根強く人々の常識のなかに根を張っている。そのような現代人の意識をディプログラミング(脱洗脳)することは極めて難しいだろう。
しかし、少子化、年金、介護、環境問題、これらすべてを根本的に何とかするには、現代人の意識の大転換が必要だと思う。したがって、その方向に向けて私なりに出来ることはやっていこうと思う。
とは言うものの、昨日、今日とで7件ほど新しい依頼や用件が、手紙やメールや電話で入った。もちろん、それ以前から話のあった依頼の、その後の経過、進展や具体的な日時の交渉などを入れたら、そうした業務連絡は2日間で20件ほどになると思う。これは、もはや私の処理能力を遥かに越えており、この先さらに新しい依頼を受けることは物理的に不可能である。
私は武術の研究、それも身体を通しての実践研究が本業であり、講演やインタビューを受けるのは、それに付随した活動である。これ以上そうしたことに時間をとられ、稽古研究の時間を失くすことは私自身の存在理由を危うくすることになる。
以上の理由により、当分の間新しい御依頼はお受けできませんので悪しからず御了承下さい。もし、それでもどうしてもという方は、御依頼の種類にもよりますが、例えば近々では名古屋での講習会が、まだ若干余裕があるようですので、筆力のあるライターの方と、この講習会に来て頂き、体を動かしつつ体験をされれば、打ち上げもありますし、2000字や3000字ならすぐに埋まると思います。体験されて、その場ですぐ要を得たラフ原稿が書けるようなライターの方なら、私としても大歓迎ですので、そのような御依頼ならお受け致しますが、それ以外は「私がかねてからお会いしたいと望んでいた方との対談」といった場合を除き、当分の間お受け出来ませんので、何卒ご了解下さい。
以上1日分/掲載日 平成19年6月9日(土)
9日は、来館を楽しみにしていたM氏への連絡の行き違いから(私が連絡したつもりで忘れていた)、M氏が他に予定を入れていて来れなくなったため、突然時間が空いた。「まあそれはそれでやらなければならないことが山積みしているから…」と思ったが、いろいろM氏に聞きたいと思っていたせいか、その高まっていたテンションの糸が切れたようで、久しぶりに気分が急降下してしまった。
折も折、ちょうど届いていた『中央公論』誌7月号に『逝きし世の面影』の著者、渡辺京二先生と私との往復書簡が載っており、そこに私が江戸時代の自然の豊かさに目が眩むほどの懐かしさと羨ましさを感じたことが出ていただけに、現代日本の、そしてこれからの日本の姿への絶望感が一気に体じゅうに毒がまわる早さで行き渡ってしまい、しばし呆然としてしまった。
それは、この自転車操業のようにして環境も人の心も食い荒らしながらバク進を続ける時代への絶望感である。普段はここ最近の猛烈な忙しさにまぎれ、また私のやっていることが直接我が身に迫る切実さに対応する武術というものであるお蔭で、その絶望感が私の意識の中にハッキリと浮上しないで済んでいたのだろう。
畏友の名越康文氏も似たようなところがあるようだが、猛烈な忙しさに辟易としながらも、その忙しさが途切れると一気に時代の矛盾か、何か得体の知れないものが、ドッと降ってきて、何とも堪らない精神状態になる。こんな時、「あなたの寿命もあと三ヶ月」などと言われたら、ずいぶんと"生きる"ということが輝くのではないかなどとさえ思ったりする。
それでも何だかんだとやる事は山ほどあるので、それらをノロノロとやっているうちに深夜になった。そして午前3時過ぎ、このところしばしば深夜に鳴くホトトギスの声を聴く。先月の下旬、宮城の山中や佐渡でも聴いたこの声に、落ちていた気分がフト浮かぶきっかけを貰った。ホオジロのような明るい声にくらべたら一種もの哀しいホトトギスの声で、どうして気分が浮かぶキッカケがつかめたのか、その理由はよく分からないが、この声は江戸時代どころか、もっと遥かに時代を遡った時から変わっていないのだろうなという思いが私のなかの何かを元気づけたのかもしれない。
その時から1時間ほど、最近得た足裏の垂直離陸と体幹の働きを打剣の稽古を通して探り、それなりに得るとことがあった。
そして10日は千代田の講習会。11日はある剣道の方に私の技の解説。12日は川崎の柔道場で『ナンだ』収録前に南原清隆氏から要請のあった私の技の体験をするミニ講習会。11日も12日も私の技を体験された方が大変熱心だったので、私もその時間は、さまざまな事を忘れて没入できた。
剣術では裏鎬の返し方や、鍔競り状態になった時、両手で竹刀を持ったまま切込入身に入って相手を崩すという新しい展開に気づいた。対柔道では、相手に組まれた状態のまま坐り込むようにする一種の捨身技を案出。ただ、これが様々な状況下でどこまで有効なのかはこれから試みてみなければ分からない。ただ、上半身と下半身が単なるうねり系では決して得られない新たな連動協調の働きに少しずつ気づき出していることは確かなように思う。
もっとも、こうした新しい技に気づいた直後に、こうした個々の技は単なる手がかりであり、それらを乗り越えてその先にある質の違った世界へと行かなければならないと思った。そうでなければ新しい技は進歩を遅らせる要素になってしまう。このようなことは以前から考えていたが、その思いが一層強くなったということは、私を取り巻く環境が更にきつくなっているという事なのかも知れない。
まあ私個人の事情はともかく、時代状況がきついことはまぎれもない。そうした時代にあって、人々が人体の精妙な働きそのものに関心を持ち、ハイテク機器の進展よりもそうした我が身が行なう不思議な働きに深みのある楽しさを感じられれば、人間が生きているということの意味そのものを根本的に問い直そうとする潮流も出て来るのではないかと、フト夢のようなことを思ったりする。夢かもしれないが、そう思っていれば、またこれから気分が落ちた時、まだ何とか浮かび上がりやすいのではないかと思ったりしている。
しかし、今この時代に私が生を享けたことは紛れもない。どんな嘆かわしい時代であろうと、ひどい時代であろうと、いまこの時代に私が生きていることは紛れもない。「人間の運命が完璧に決まっていて、同時に完璧に自由である」という、私が21歳の時の気づきを「体感をもって実感したい」という、私が武の世界に志したその原点に返れば、どのような状況のなかでも自分が生きているという事を見失わないでいられるだろう。至難なことだが、私自身が現代を生きていくということは、そこを見つめていくしかないようにあらためて思った。
以上1日分/掲載日 平成19年6月14日(木)
この私のサイトを開いてから9年ほど経ち、この随感録を書く前に書いていた交遊録等を含め、いままでに本にしたら何冊か分になるほどいろいろ書いてきたと思うが、今日ほど上手く筆が運ばないことは、いままで一度もなかった。
というのも、16日から名古屋に出て講習会。その後、滋賀でも講習会があって、そこでいろいろな人と交流し、いまのような人心が荒廃している時代でも、まだまだ、いっしょう懸命な人がいるという事が感じられた一方で、本当にもうその存在の仕方自体が信じられないほど不様で、しかも社会的に責任のある立場にいる人を目のあたりにするという悲惨な体験をしたからである。こうなると、もう生きていこうという意欲が根底から削がれる思いがする。
まあ、社会の責任ある立場の人間にこれほど不様な人がいるのだから、いま世間を騒がせている年金問題のようないい加減さも出るだろうし、あきれ返るような理不尽な要求を学校に突きつける馬鹿親も出てくるのだろう。それにしても、直に不様な人に会い、壊れていく日本を直に感じるとさすがに暗然とする。
そんな私を何とかまだ踏みとどまらせているのは、やはり体を通しての技の工夫という事への意欲がまだ衰えていないからだと思うが、世間に背を向けて技の工夫にのみ没入できない自分がいて、だからこそ、まだ自分で自分を多少なりとも許せると思うが、そのために私自身が引き裂かれそうになる。
それにしても世間の人の多くは、結局仕事の取り引きなどが上手くいくかどうか、という目の前の切実な問題に気持ちが奪われ、人の心も環境も壊れていく日本に暗然としている暇もないのだろうか?
最近は身体の使い方でも、また武術の技法上も、少なからぬ気づきもあるのですが、その事を書こうとすると、「そんな事を書いているどころじゃないだろう」と、まるで誰かに時代の矛盾を突きつけられるようにして書けなくなってしまいます。
私の動きに関心のある方は、東京では池袋コミュニティカレッジやIACの講座などにお越し下さい。東京以外では、6月29日は朝日カルチャーセンター湘南、7月7日は熊本日日新聞社主催の公開講座「DO がくもん」(熊本学園大学共催)、7月29日は神戸女学院大学の公開講座などがあります。
以上1日分/掲載日 平成19年6月20日(水)
朝日新聞朝刊の「疑問解決モンジロー」というコーナーに、「なんば」について私への取材も含めた記事が載った昨日25日、私は午後からテレビ朝日のスタジオで「ナンだ!?」の収録を行なっていた。この番組に関しては、この番組をメインで引っ張られている南原清隆氏の私に対する関心の持ち方が通り一辺のものではない事を知り、受けることにしたのだが(畏友、名越康文氏からの推薦があったこともあり)、南原氏はじめ、出演者の方々が仕事としてのリアクションを越えた関心の持ち方をされたので、私としても今までのテレビ出演のなかで最もやりやすかった。
と同時に、私自身にとって新鮮だったのは、この収録が始まる直前、少し緊張している自分を発見できたことだった。というのも、前回20日の随感録に書いたように、最近は様々なところで「壊れていく日本」を見せつけられることが多く、気持ちも塞ぎがちになっていたからである。緊張するというのは、自分のなかに、まだ生きていこうという意欲がある証でもある。南原氏の、ただ表面的に驚いてみせるのではない司会進行にも好意が持てた。南原氏の関心が単に番組の企画上だけではなかったらしい事は、収録後、私がこの番組の相手役として出てもらった国士舘大学の柔道部員の選手達にいろいろ技の解説をしている間も、私に同行していた陽紀にいろいろ質問をして学ぼうとされている南原氏自身の態度にも表れていた。編集を経てどのような番組となるかは分からないが、私としては収録中嫌な思いをしなくて済んだことだけで十分ありがたかった。
それからこの番組の中でもやはり話題になったが、パイレーツの桑田真澄投手の最近の思いがけない活躍によって、桑田投手関連の話のなかに私の事が出ることがしばしばあり、メディアからの問い合わせがまた出始めている。桑田氏とはいまも時折メールをやりとりしているが、別に私が何を教えたという事もない。ただ非常に真面目で研究熱心な人柄なので、桑田氏が来ると思わずいろいろと話をしてしまうという、そういう間柄である。そうした話や私の動きから、桑田氏は桑田氏なりに気づきを得たのだろう。まあ、守備に関しては桑田氏も「先生に出会わなかったら、いまのような守備は出来ていませんよ。守備は僕のいままでで今が最高なんです」と、昨年秋、熱く語ってくれたし、私も、守備は私の武術が野球に一番ハッキリと生かされるとは思うが、投球に関しては私自身、自分の打剣がまだまだなので桑田氏にどうこう言えるほどのものはない。
ただ、それでもその打剣がこのところ明らかに変わってきているのは、明治期に奈良十津川の山に隠れるように住んでいた超絶的身体能力を持った異風の剣客中井亀治郎の逸話を知った事が少なからず関わっていると思われる。その数々の逸話のなかでも、私に最も大きな影響を与えたのは、山崩れの後のガレ場の上から空の醤油樽を転がし、これを棒で叩きながら一気に駆け下りる、という事を剣術の稽古のために行なっていたということである。亀治郎は、そうした稽古を積んでいたため、逃げる鹿に追いついて、これを組み伏せたという。まさに超人的な体幹操作能力である。
かつての名人・達人といった武術家達のまるで作り話のような神技的エピソードは、私自身書けばそれだけで本が数冊出来るほど知っているが、そうした話が私の体捌きに直に影響を与えたことは滅多にない。しかし、この中井亀治郎のエピソードは、なぜか妙なリアル感があって、最近はその話を思い出して体を動かすと何ともいえない気づきをもらう事が度々ある。
当然のことだが、こういう話を書いていれば筆も進むし心身のためにいい。
私の気分が落ち込むと、いろいろ気づかってひどく心配して下さる方もあるので、出来るだけ今日のような随感録にしていきたいと思いますが、なんといっても随感録ですから、その時の気分のままに書くことを御容赦下さい。
追記
今日は「報道ステーション」の撮影で、松岡修造氏来館。松岡氏にも驚いて頂いたようで、また忙しい事になりそうだ。
以上1日分/掲載日 平成19年6月27日(水)