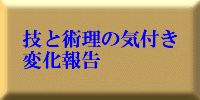 |
'01 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 '00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 '99 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2000年6月4日(日)
忙しさに追われ、この『技と術理〜』の欄はずいぶん日があいてしまったように思う。
ひとつは書こう書こうと思いつつ、一区切ついたところでと思っていたからかもしれない。その一区切がなかなかつかず、今ようやく、高崎であった同志会の合宿からの帰りの車中でこれを書いている。
先月下旬の関西・岡山・仙台での稽古会、それに今月に入って都内での定例稽古に同志会の合宿と、何十人といういろいろなタイプの人達と手を交えて何よりも痛感したことは、いわゆるタメや予備動作なく一気に発力することの重要さである。
つまり具体例を挙げれば、空手道心道会の宇城憲治先生のように、相手に触れた状態から一気に内部に浸透する突きが出せるようにならねば武術としてはどうしても片手落ちだということである。
よく柔術は相手の力を利用するというが、当身を用いずほとんどすべて投げ技で処理する体系であった起倒流柔術の名手・加藤有慶は門人・八木宗安の居宅の前を通ると、宗安の家の前に懸っている小橋の橋板を竹の杖で突き鳴らしながら「宗安いるか」と声をかけるのが通例だったというが、その突く音はカンカンと耳につく高い音で、これは他の誰も有慶のようには出来なかったらしい。他の者が真似るとただトントンという音だったという。これは有慶の発力がタメなく一気に高いエネルギーを出せたことを物語っていると思う。
また武術ではないが゛術と呼べるほどのもの゛を会得していたと思われる整体協会の野口晴哉先生は、小柄軽量な体格にもかかわらず、体重計に両手の拇指をあててグンと沈ませると一気に針が野口先生の体重よりはるかに重いところまで動いたらしいが、門下生で誰一人そこまで針を動かせた者はいないという。
こうしたことはおそらくは体の内部の並列処理的使い方により、一気にあるレベル以上の力を出したのではないかと思われるが、これは所謂ウエイト・トレーニング等による訓練法では不可能であろう(もっとも、きわめて特殊な設計がなされたウエイト使用のトレーニング法、たとえば肥田春充翁の鍛練などであればまた別であろうが)。
いま述べたことは以前からも思っていたことだが、今回より一層ハッキリと浮び出てきたのは、吸気による体の使い方(厳密に言えば、吸気というより胸を解放することにより、胸内圧が低くなり、自然と空気が入ってくる状態)の有効性が5月下旬から各地をまわって確認されたことも大きいと思う。
鎌柄の有効性、また私より体格も大きく力も強い人とがっぷりと相撲の形で四つに組み押し合っても、いままでは考えられない寄りが出来るようになったことなどは、私にいままでとは明らかに違う不思議な感覚を拓きつつある。
胸の圧力が高まらないというのは、ひとつには「これは出来ないかもしれない」という精神的不安を生じさせにくくなっており、そうしたことも吸気による技の有効性を成立させている要素なのかもしれない。
忙しさに追われ、この『技と術理〜』の欄はずいぶん日があいてしまったように思う。
ひとつは書こう書こうと思いつつ、一区切ついたところでと思っていたからかもしれない。その一区切がなかなかつかず、今ようやく、高崎であった同志会の合宿からの帰りの車中でこれを書いている。
先月下旬の関西・岡山・仙台での稽古会、それに今月に入って都内での定例稽古に同志会の合宿と、何十人といういろいろなタイプの人達と手を交えて何よりも痛感したことは、いわゆるタメや予備動作なく一気に発力することの重要さである。
つまり具体例を挙げれば、空手道心道会の宇城憲治先生のように、相手に触れた状態から一気に内部に浸透する突きが出せるようにならねば武術としてはどうしても片手落ちだということである。
よく柔術は相手の力を利用するというが、当身を用いずほとんどすべて投げ技で処理する体系であった起倒流柔術の名手・加藤有慶は門人・八木宗安の居宅の前を通ると、宗安の家の前に懸っている小橋の橋板を竹の杖で突き鳴らしながら「宗安いるか」と声をかけるのが通例だったというが、その突く音はカンカンと耳につく高い音で、これは他の誰も有慶のようには出来なかったらしい。他の者が真似るとただトントンという音だったという。これは有慶の発力がタメなく一気に高いエネルギーを出せたことを物語っていると思う。
また武術ではないが゛術と呼べるほどのもの゛を会得していたと思われる整体協会の野口晴哉先生は、小柄軽量な体格にもかかわらず、体重計に両手の拇指をあててグンと沈ませると一気に針が野口先生の体重よりはるかに重いところまで動いたらしいが、門下生で誰一人そこまで針を動かせた者はいないという。
こうしたことはおそらくは体の内部の並列処理的使い方により、一気にあるレベル以上の力を出したのではないかと思われるが、これは所謂ウエイト・トレーニング等による訓練法では不可能であろう(もっとも、きわめて特殊な設計がなされたウエイト使用のトレーニング法、たとえば肥田春充翁の鍛練などであればまた別であろうが)。
いま述べたことは以前からも思っていたことだが、今回より一層ハッキリと浮び出てきたのは、吸気による体の使い方(厳密に言えば、吸気というより胸を解放することにより、胸内圧が低くなり、自然と空気が入ってくる状態)の有効性が5月下旬から各地をまわって確認されたことも大きいと思う。
鎌柄の有効性、また私より体格も大きく力も強い人とがっぷりと相撲の形で四つに組み押し合っても、いままでは考えられない寄りが出来るようになったことなどは、私にいままでとは明らかに違う不思議な感覚を拓きつつある。
胸の圧力が高まらないというのは、ひとつには「これは出来ないかもしれない」という精神的不安を生じさせにくくなっており、そうしたことも吸気による技の有効性を成立させている要素なのかもしれない。
2000年6月5日(月)
3日、4日と同志会の合宿に招かれて高崎へ行った帰りに、ここ数年来、一度は訪ねたいと思っていた約30年来の武友である小用茂夫氏の稽古会に寄らせていただいた。
新陰流の剣術では小用氏の門下で最古参のS氏と竹刀を合わせ、大変気づかされるところがあったのは幸運だった。
私の剣術のベースである鹿島神流の体系が、小用氏の親友である前田英樹氏との立ち合いをキッカケにおおいに見直さねばならないことを悟ったのがもう16年も前だが、その後゛井桁崩し゛の気づきから始まる一連の私の武術の大転換で、それまで私が絶対的といってもいいほど信奉していた強い腰の反りや、前足の爪先を外側に踏み開いた゛ソの字立ち゛が消え、私の剣術の体系はほとんど崩壊してしまった。
その後、部分的に゛車の構゛が出たり、突き技への対応が、以前とはまったく正反対に太刀を手之内でめぐらせて制するとか、いくつかの部分的な発見はあったが、組太刀の体系といったものは消えてしまったに等しい状態がずっと続いている。
この状況となってから、もう8年ぐらいだろうか。いまもって私のなかでは体系だった剣の型など出来る気配はまったくない。
ひとつには、私が無住心剣術など今では伝書のみしか残っていないような流派の術理に心ひかれて研究しているうち、それぞれの流派の長所や問題点が私なりにではあるが感じられてきて、いったい私はどういう形態の剣術を目指しているのか、それがきわめて見えにくくなってきているからかもしれない。
そして剣術の場合、いわゆる型稽古なら鹿島神流にせよ、あるいは他の何かの流儀の型なりをそれらしく真似していれば、それはそれで何かやったような気分になってしまうという落し穴が、直に皮膚を触れ合わせる体術よりも多く開いているように思う。
そのため私はこれまで崩壊した私の剣術の体系を、崩壊させたまま手をつけずにきた。
そして昨日S氏と竹刀を合わせ、私が手をつけずに崩壊させたままにしてきた剣術の体系は、今後自然と私のなかで、きわめて必然性を持って組み上がってこない限りは、適当に体系化してまとめたりは決してするまいと、あらためて心に決めたのである。
その日(私のなかで、私のオリジナルの剣術の体系が組み上がってくる日)がいつかは来るのか、まったくわからないが、いまの私はとにかく体術や手裏剣術等を通して動きの質を転換させることを主に稽古してゆこうと思っている。
稽古後、近くの小用氏行きつけの居酒屋で数時間門人の方共々、武術談義に花が咲き、たいへん楽しく貴重なひとときを過させていただいた。
ここであらためて厚く御礼を申し上げたい。
3日、4日と同志会の合宿に招かれて高崎へ行った帰りに、ここ数年来、一度は訪ねたいと思っていた約30年来の武友である小用茂夫氏の稽古会に寄らせていただいた。
新陰流の剣術では小用氏の門下で最古参のS氏と竹刀を合わせ、大変気づかされるところがあったのは幸運だった。
私の剣術のベースである鹿島神流の体系が、小用氏の親友である前田英樹氏との立ち合いをキッカケにおおいに見直さねばならないことを悟ったのがもう16年も前だが、その後゛井桁崩し゛の気づきから始まる一連の私の武術の大転換で、それまで私が絶対的といってもいいほど信奉していた強い腰の反りや、前足の爪先を外側に踏み開いた゛ソの字立ち゛が消え、私の剣術の体系はほとんど崩壊してしまった。
その後、部分的に゛車の構゛が出たり、突き技への対応が、以前とはまったく正反対に太刀を手之内でめぐらせて制するとか、いくつかの部分的な発見はあったが、組太刀の体系といったものは消えてしまったに等しい状態がずっと続いている。
この状況となってから、もう8年ぐらいだろうか。いまもって私のなかでは体系だった剣の型など出来る気配はまったくない。
ひとつには、私が無住心剣術など今では伝書のみしか残っていないような流派の術理に心ひかれて研究しているうち、それぞれの流派の長所や問題点が私なりにではあるが感じられてきて、いったい私はどういう形態の剣術を目指しているのか、それがきわめて見えにくくなってきているからかもしれない。
そして剣術の場合、いわゆる型稽古なら鹿島神流にせよ、あるいは他の何かの流儀の型なりをそれらしく真似していれば、それはそれで何かやったような気分になってしまうという落し穴が、直に皮膚を触れ合わせる体術よりも多く開いているように思う。
そのため私はこれまで崩壊した私の剣術の体系を、崩壊させたまま手をつけずにきた。
そして昨日S氏と竹刀を合わせ、私が手をつけずに崩壊させたままにしてきた剣術の体系は、今後自然と私のなかで、きわめて必然性を持って組み上がってこない限りは、適当に体系化してまとめたりは決してするまいと、あらためて心に決めたのである。
その日(私のなかで、私のオリジナルの剣術の体系が組み上がってくる日)がいつかは来るのか、まったくわからないが、いまの私はとにかく体術や手裏剣術等を通して動きの質を転換させることを主に稽古してゆこうと思っている。
稽古後、近くの小用氏行きつけの居酒屋で数時間門人の方共々、武術談義に花が咲き、たいへん楽しく貴重なひとときを過させていただいた。
ここであらためて厚く御礼を申し上げたい。
以上2日分/掲載日 平成12年6月7日(水)
2000年6月15日(木)
腰を痛め、しばらく足が遠のいていた信州の江崎義巳氏と4ヶ月ぶりに稽古する。前回、江崎氏と稽古した2月10日といえば、私にはまだ吸気による体の運用の自覚がまったくなかった頃で、体の感覚が鋭くなってきている江崎氏に体術でかなり苦労させられた記憶がある。
今日、その江崎氏に体術の技をいくつか試みたが、技の通り方がずいぶん違っていた。
なかでも座りの直入身(もともとは私のところでは両手の柾目返といっていたもので、いわゆる゛合気揚げ゛のように受が取の両手首を掴んで頑張る形態であったが、私の稽古会では受がなるべく自分が有利なような形で対応するものも崩せねば意味がないという主旨で稽古しているため、必然的に受の人間は取の両手首を掴まず、取の手の甲あたりを下やら横にいなして対応するようになってきている。そのため取は受の手に触れた瞬間に受を崩さねば技として成立せず、そうなると゛直入身゛とでも呼ぶしかない状況となってきているのである)、鎌柄、小手返、相撲の形で四つに組んでの寄り、等の技の感触には江崎氏もかなり驚いたようだった。
ここであらためて紹介するまでもないが、江崎氏は私の手裏剣術を最もよく受け継いだ人物で、その剣造りの腕と情熱は私を超えたのではないかと思えるほどであり、現在私が稽古に使っている剣は、すべて江崎氏に私の細かい希望を伝えて鍛え削り上げてもらったものである。一人信州で稽古相手もなく、ほとんど手裏剣術の稽古で感覚を研いでいるが、そのセンスにはしばしばハッとさせられる。
今日も吸気による体術の技を初めて受けた感想として、「先生の技は、以前はいきなり始まっても、今思うと『1、2、3、4、5……』という感じだったと思うんですけれど、今日の技は、何かいきなり『3、4、5……』という感じで、1と2が抜けてるような気がするんですよ。だからこちらが間に合わないんだと思うんです」とコメントしてくれた。
しかし決して私にへつらうようなことを言わない彼は、私が手裏剣の打法を見せ、「どうです、以前にくらべればうねりがなくなっているでしょう」と言うと、「いや、でもまだ何か投げてるっていう感じですよ。本当にその辺が消えれば、『えっ』と目を見張るような動きにきっとなると思いますから」と、実に率直な感想を述べてくれた。
この時私は、いままで20年以上稽古会をやってきて、かつて私が願ったような方向に来ているということにあらためて何ともいえぬ喜びを感じた。この江崎氏に限らず、松聲館の常連の吉田氏、五味氏、Y氏、恵比寿稽古会の岡田氏、地方では四国の守氏らは決して安易には受をとらず、率直かつ非常に的を射た具体的な感想や意見を述べてくれる。もちろん仙台や関西の稽古会の常連も安易に受をとらない人ばかりといってもいいほどである。
このような状況下で場がシラけることがないようにするためには、その「出来ない」という事実を私が率直に認めることと、それ以外ではかなり困難な状況設定のもとでも技が出来ることが必須であると思う(やる技やる技、皆どれもこれも「出来ません」ということになったら、誰もわざわざ時間と費用を使って稽古会に参加する気をなくしてしまうだろう)。指導者にとっては厳しい環境かもしれないが、そうしないと結局、上っ面だけの稽古になってしまう。
とにかく、江崎氏の目から見て、「まあ、それなら『おやっ』という感じですね」と言ってもらえる状況で剣を飛ばすにはどのくらいからならいいだろうかと、前へ前へと的に寄っていったら、なんと三尺(半間)ぐらいなら、うねって投げている感じがないとのことだった。
その後、なんとか一間ぐらいまでその感じで打てたが、これが四間でも出来るとなったら、なるほど今とはまったく質の違う動きが出来ているだろう、と私自身も納得がいった。
昔日、太刀を僅か三寸動かしただけで、ビュンと刃音がしたというのも、今日とはまったく違った体の運用法を行なっていたからに相違なかろう、ということがあらためて確認できた気がした。
今日、武道界の大家といわれる人達の一番の問題点は、往時にくらべはるかに落ちた自らの術技レベルに危機感を持たず、周囲のよく観る眼を持たぬ人達からの「素晴らしいですね」というおだての言葉に易々とのってしまっていることではないだろうか。
「武道で精神を修養する」というが、武の世界で精神が鍛えられるのは、「出来るか、出来ないか」というギリギリの状況下という設定があったからであろう。指導者なら、より向上を目指そうとする者なら、常により困難な状況下に自らを置いて、自らの技を研いでいくべきではないだろうか。
「武道は技よりも精神が大事だ」という言葉は、術技的に古人にならぶほど具体的に技が使えるようになってから口にして初めて様になると思うのだが……。
腰を痛め、しばらく足が遠のいていた信州の江崎義巳氏と4ヶ月ぶりに稽古する。前回、江崎氏と稽古した2月10日といえば、私にはまだ吸気による体の運用の自覚がまったくなかった頃で、体の感覚が鋭くなってきている江崎氏に体術でかなり苦労させられた記憶がある。
今日、その江崎氏に体術の技をいくつか試みたが、技の通り方がずいぶん違っていた。
なかでも座りの直入身(もともとは私のところでは両手の柾目返といっていたもので、いわゆる゛合気揚げ゛のように受が取の両手首を掴んで頑張る形態であったが、私の稽古会では受がなるべく自分が有利なような形で対応するものも崩せねば意味がないという主旨で稽古しているため、必然的に受の人間は取の両手首を掴まず、取の手の甲あたりを下やら横にいなして対応するようになってきている。そのため取は受の手に触れた瞬間に受を崩さねば技として成立せず、そうなると゛直入身゛とでも呼ぶしかない状況となってきているのである)、鎌柄、小手返、相撲の形で四つに組んでの寄り、等の技の感触には江崎氏もかなり驚いたようだった。
ここであらためて紹介するまでもないが、江崎氏は私の手裏剣術を最もよく受け継いだ人物で、その剣造りの腕と情熱は私を超えたのではないかと思えるほどであり、現在私が稽古に使っている剣は、すべて江崎氏に私の細かい希望を伝えて鍛え削り上げてもらったものである。一人信州で稽古相手もなく、ほとんど手裏剣術の稽古で感覚を研いでいるが、そのセンスにはしばしばハッとさせられる。
今日も吸気による体術の技を初めて受けた感想として、「先生の技は、以前はいきなり始まっても、今思うと『1、2、3、4、5……』という感じだったと思うんですけれど、今日の技は、何かいきなり『3、4、5……』という感じで、1と2が抜けてるような気がするんですよ。だからこちらが間に合わないんだと思うんです」とコメントしてくれた。
しかし決して私にへつらうようなことを言わない彼は、私が手裏剣の打法を見せ、「どうです、以前にくらべればうねりがなくなっているでしょう」と言うと、「いや、でもまだ何か投げてるっていう感じですよ。本当にその辺が消えれば、『えっ』と目を見張るような動きにきっとなると思いますから」と、実に率直な感想を述べてくれた。
この時私は、いままで20年以上稽古会をやってきて、かつて私が願ったような方向に来ているということにあらためて何ともいえぬ喜びを感じた。この江崎氏に限らず、松聲館の常連の吉田氏、五味氏、Y氏、恵比寿稽古会の岡田氏、地方では四国の守氏らは決して安易には受をとらず、率直かつ非常に的を射た具体的な感想や意見を述べてくれる。もちろん仙台や関西の稽古会の常連も安易に受をとらない人ばかりといってもいいほどである。
このような状況下で場がシラけることがないようにするためには、その「出来ない」という事実を私が率直に認めることと、それ以外ではかなり困難な状況設定のもとでも技が出来ることが必須であると思う(やる技やる技、皆どれもこれも「出来ません」ということになったら、誰もわざわざ時間と費用を使って稽古会に参加する気をなくしてしまうだろう)。指導者にとっては厳しい環境かもしれないが、そうしないと結局、上っ面だけの稽古になってしまう。
とにかく、江崎氏の目から見て、「まあ、それなら『おやっ』という感じですね」と言ってもらえる状況で剣を飛ばすにはどのくらいからならいいだろうかと、前へ前へと的に寄っていったら、なんと三尺(半間)ぐらいなら、うねって投げている感じがないとのことだった。
その後、なんとか一間ぐらいまでその感じで打てたが、これが四間でも出来るとなったら、なるほど今とはまったく質の違う動きが出来ているだろう、と私自身も納得がいった。
昔日、太刀を僅か三寸動かしただけで、ビュンと刃音がしたというのも、今日とはまったく違った体の運用法を行なっていたからに相違なかろう、ということがあらためて確認できた気がした。
今日、武道界の大家といわれる人達の一番の問題点は、往時にくらべはるかに落ちた自らの術技レベルに危機感を持たず、周囲のよく観る眼を持たぬ人達からの「素晴らしいですね」というおだての言葉に易々とのってしまっていることではないだろうか。
「武道で精神を修養する」というが、武の世界で精神が鍛えられるのは、「出来るか、出来ないか」というギリギリの状況下という設定があったからであろう。指導者なら、より向上を目指そうとする者なら、常により困難な状況下に自らを置いて、自らの技を研いでいくべきではないだろうか。
「武道は技よりも精神が大事だ」という言葉は、術技的に古人にならぶほど具体的に技が使えるようになってから口にして初めて様になると思うのだが……。
以上1日分/掲載日 平成12年6月17日(土)