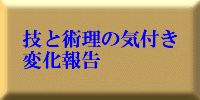 |
'01 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 '00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 '99 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
2000年10月6日(金)
東北から帰った9月29日、そのまま東京で人と会い、終電を逃して深夜バス。
そして、その翌日も、上京中の名越氏らとカルメン・マキライブに行き(久しぶりに行ったが、マキさんの迫力は流石というしかない)、その後また、名越氏の新しい知り合いに紹介されたりして終電。
……と、1週間以上外出続きの強行軍がたたってか、喉がおかしくなって、数日間、寝込むほどではなかったが、典型的な風邪症状で、2日、3日、4日は、まったく稽古はせず、ほとんど体を動かすことさえなく過ごした。
6日は都内で稽古会があるので、5日の日は少し薪づくりや片づけなどで体を動かしたが、まだ本調子とは言い難かった。
ところが6日の稽古の日、3時間ずっと体がもつだろうかと危んでいたのだが、いざ稽古を始めてみると案に相違して思っていたより動き、しかもこの間までとはまたひと味違った動きである。
腕が働きすぎないように、あくまでも脇役にということは、仙台の稽古会での気づきだったが、今回それを試みたところ、仙台での稽古で気づいた時より、何か身についている気がするのである。
そのうち、手が出すぎないように、ということに関して「ウシカモシカも群れから離れるからライオンの餌食になるので、同じウシカモシカでも群れの先頭で群れと共に走れば、ライオンも踏み殺してしまう働きをするのだ」というたとえを思いつき、技をいろいろな人に試みているうち、このたとえの変形バージョンとして「鉋(カンナ)くずは簡単にちぎれるでしょうけれど、まだ削れる前の太い柱の一部となっている時はちぎろうにもちぎれないでしょう」というような、まあかなり強引なこじつけのようなものまで思いついて、解説しながら稽古に熱が入ったので3時間も苦にはならなかった。
この手、腕と体全体との一体化であるが、たとえば両手を、相手が両手で持って、いなしありで、正面からこちらが前へ出るのを阻止しようとしている時、腕を体に吸い込むようにしつつ前に出るのだが、この吸い込みつつ前に出る、という体感覚は、なんとも微妙。
体は割れているのだが、一体感が必要だし、硬直していてはもとより駄目だが、ただ脱力しているのとはまったく違う。なんというかきわめて平凡なたとえだが、服などが体にダブダブでもなく窮屈でもなく、ピッタリしているという感じだろうか。
最近以前よりも動きが出来るようになってくると、表現がドンドン平凡なものになってくる。不思議な気もするが、あるいはこれが当然なのかもしれない。
しかし、さらなる動きの質の向上のためには、また逆説的なたとえや表現を使わなければならない時期も必要なように思う。
ただまあ、それも時期がくればまた自然とそうなるだろう。
東北から帰った9月29日、そのまま東京で人と会い、終電を逃して深夜バス。
そして、その翌日も、上京中の名越氏らとカルメン・マキライブに行き(久しぶりに行ったが、マキさんの迫力は流石というしかない)、その後また、名越氏の新しい知り合いに紹介されたりして終電。
……と、1週間以上外出続きの強行軍がたたってか、喉がおかしくなって、数日間、寝込むほどではなかったが、典型的な風邪症状で、2日、3日、4日は、まったく稽古はせず、ほとんど体を動かすことさえなく過ごした。
6日は都内で稽古会があるので、5日の日は少し薪づくりや片づけなどで体を動かしたが、まだ本調子とは言い難かった。
ところが6日の稽古の日、3時間ずっと体がもつだろうかと危んでいたのだが、いざ稽古を始めてみると案に相違して思っていたより動き、しかもこの間までとはまたひと味違った動きである。
腕が働きすぎないように、あくまでも脇役にということは、仙台の稽古会での気づきだったが、今回それを試みたところ、仙台での稽古で気づいた時より、何か身についている気がするのである。
そのうち、手が出すぎないように、ということに関して「ウシカモシカも群れから離れるからライオンの餌食になるので、同じウシカモシカでも群れの先頭で群れと共に走れば、ライオンも踏み殺してしまう働きをするのだ」というたとえを思いつき、技をいろいろな人に試みているうち、このたとえの変形バージョンとして「鉋(カンナ)くずは簡単にちぎれるでしょうけれど、まだ削れる前の太い柱の一部となっている時はちぎろうにもちぎれないでしょう」というような、まあかなり強引なこじつけのようなものまで思いついて、解説しながら稽古に熱が入ったので3時間も苦にはならなかった。
この手、腕と体全体との一体化であるが、たとえば両手を、相手が両手で持って、いなしありで、正面からこちらが前へ出るのを阻止しようとしている時、腕を体に吸い込むようにしつつ前に出るのだが、この吸い込みつつ前に出る、という体感覚は、なんとも微妙。
体は割れているのだが、一体感が必要だし、硬直していてはもとより駄目だが、ただ脱力しているのとはまったく違う。なんというかきわめて平凡なたとえだが、服などが体にダブダブでもなく窮屈でもなく、ピッタリしているという感じだろうか。
最近以前よりも動きが出来るようになってくると、表現がドンドン平凡なものになってくる。不思議な気もするが、あるいはこれが当然なのかもしれない。
しかし、さらなる動きの質の向上のためには、また逆説的なたとえや表現を使わなければならない時期も必要なように思う。
ただまあ、それも時期がくればまた自然とそうなるだろう。
以上1日分/掲載日 平成12年10月9日(月)
2000年10月15日(日)
昨日、今日と道場で稽古をして、以前、PHP研究所から『武術の新人間学』を書いた5年ほど前に、この本の中で解説をした゛一足立゛の意味について、小手返や剣術等であらためて気づかされることがあった。
現在私が行なっている小手返は、受がしっかりと握り拳をつくって手首を固め、その上で、こちらの手を振りほどいて逃げようとしてもいい、という受側にとって、出来るだけ、この技にかからないように防いでもらう、という状況下で行なっているが、このようにすると、多くの人のなかには、さすがに大変な粘りを発揮する人も出てきて、容易に技が決まらないことがある。そうした人は、私の技の進展の度合をみる貴重なものさしとして有難く思っているが、風邪が抜けてきてから、なぜか、そういう粘っこい人にも、この小手返が利くようになってきた。
その主な理由は、小手を返す時、ふつうはどうしても腰がめぐり、上体がそれにつれて向き変わるため体がうねって、気配が出て、相手にその動きのパターンをさとられて、グッと頑張られたり、振りほどかれたりするのだが、どうやら、私の体の振り返る気配が以前より消え、その速度自体も早くなったようなのである。
その理由が13日頃までは、よくわからなかったのだが、どうも゛一足立゛に関係があるらしいことが、14日稽古していてわかってきた。
どういうことかというと、体を動かす時、どこかを踏ん張って支点をつくることを嫌って、私は両膝をぬき、体を宙に浮かすのだが、そうすると体がアメーバー的状態になって、足を踏ん張ってそこを起点にして起こすうねりとは違うが、ある種のうねりというか、ゼリーがぷるんぷるんとふるえるような状態になるらしいのである。そのため、どうしても動きが遅くなっていたようなのである。
そのため、小手返で体の向きを変える時、瞬間に一足立となり、その一足立をうねりの起点としてではなく、そこを基準に左右の半身が入れ換わる線として使うと、体がうねりながら向きが変わる場合にくらべ、唐突に脈絡なく変わることができるらしいのである。
このことに気づいてから、剣術で正眼で待峙している相手に対し、その面を打ち込んでいき、相手がそれを防ごうとした瞬間、太刀を上に抜いて相手の右籠手を打つ゛影抜゛という技に、この一足立を応用したところ、最近は私の抜きに対してかなり適応してきていたT氏が一方的に打たれ、感想を聞いてみると、「まるではじめから先生の竹刀が右籠手に向って飛んでくるような気がするんです」とのことだった。
言葉でいえばこれだけのことだが、こんなことが私のように凡庸な者には現実に気づくのに5年もかかってしまった。古人の妙技はこんな気づきのおそらく千倍万倍だろう。
あらためて古人のレベルの高さを思わずにはいられなかった。
昨日、今日と道場で稽古をして、以前、PHP研究所から『武術の新人間学』を書いた5年ほど前に、この本の中で解説をした゛一足立゛の意味について、小手返や剣術等であらためて気づかされることがあった。
現在私が行なっている小手返は、受がしっかりと握り拳をつくって手首を固め、その上で、こちらの手を振りほどいて逃げようとしてもいい、という受側にとって、出来るだけ、この技にかからないように防いでもらう、という状況下で行なっているが、このようにすると、多くの人のなかには、さすがに大変な粘りを発揮する人も出てきて、容易に技が決まらないことがある。そうした人は、私の技の進展の度合をみる貴重なものさしとして有難く思っているが、風邪が抜けてきてから、なぜか、そういう粘っこい人にも、この小手返が利くようになってきた。
その主な理由は、小手を返す時、ふつうはどうしても腰がめぐり、上体がそれにつれて向き変わるため体がうねって、気配が出て、相手にその動きのパターンをさとられて、グッと頑張られたり、振りほどかれたりするのだが、どうやら、私の体の振り返る気配が以前より消え、その速度自体も早くなったようなのである。
その理由が13日頃までは、よくわからなかったのだが、どうも゛一足立゛に関係があるらしいことが、14日稽古していてわかってきた。
どういうことかというと、体を動かす時、どこかを踏ん張って支点をつくることを嫌って、私は両膝をぬき、体を宙に浮かすのだが、そうすると体がアメーバー的状態になって、足を踏ん張ってそこを起点にして起こすうねりとは違うが、ある種のうねりというか、ゼリーがぷるんぷるんとふるえるような状態になるらしいのである。そのため、どうしても動きが遅くなっていたようなのである。
そのため、小手返で体の向きを変える時、瞬間に一足立となり、その一足立をうねりの起点としてではなく、そこを基準に左右の半身が入れ換わる線として使うと、体がうねりながら向きが変わる場合にくらべ、唐突に脈絡なく変わることができるらしいのである。
このことに気づいてから、剣術で正眼で待峙している相手に対し、その面を打ち込んでいき、相手がそれを防ごうとした瞬間、太刀を上に抜いて相手の右籠手を打つ゛影抜゛という技に、この一足立を応用したところ、最近は私の抜きに対してかなり適応してきていたT氏が一方的に打たれ、感想を聞いてみると、「まるではじめから先生の竹刀が右籠手に向って飛んでくるような気がするんです」とのことだった。
言葉でいえばこれだけのことだが、こんなことが私のように凡庸な者には現実に気づくのに5年もかかってしまった。古人の妙技はこんな気づきのおそらく千倍万倍だろう。
あらためて古人のレベルの高さを思わずにはいられなかった。
以上1日分/掲載日 平成12年10月18日(水)