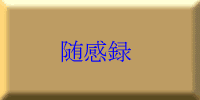 |
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2001年 2005年 2009年 2013年 2002年 2006年 2010年 2014年 2003年 2007年 2011年 2016年 2004年 2008年 2012年 |
先日、私のツイッターで予告しておいたが、私が月2回アップしている「夜間飛行」のメールマガジン『風の先・風の跡』の中で、私が福岡要氏と「日照雨」と題して行なっている往復書簡で、いま話題の小保方問題に関連し、科学的な行為とは何か、という事に関して福岡氏に秀逸な文章を書いて頂いたので、それをこの「随感録」で紹介したい。紹介するのは3回に分けて福岡氏が述べられている、その第1回目である。2回目は今週初めの16日に私のメールマガジンでアップされているので、ご関心のある方はそちらをどうぞ。
http://yakan-hiko.com/kono.html
3回目は7月7日アップのメールマガジンに掲載の予定です。
■科学を考える:前編
甲野先生
お忙しい中、お返事ありがとうございました。こちらは、ようやく田植えも終わり、カエルの声が町いっぱいに響く季節になりました。過分なご評価をいただいて、ただただただただ、恐縮でございます。
先日(5月18日)池袋で行われた「この日の学校」でも、大変お世話になりました。山本豊津氏との対談、最前列でわっくわくしながら拝聴しておりました。「美」術と「武」術、どちらも立ち居振る舞いにこそ、というお話しが特に心に残っております。
名越先生の会の打ち上げにも我儘を申し上げて参加させていただき、とても勉強になりました。聞くお話し、お話し、一つ一つが面白く、身体に響いてきました。新参者のぽっと出のお邪魔ものにも、皆様温かく迎えていただき、ありがとうございました。名越先生の、「空海のような後継者問題」のお話し、今後どう変わっていくのか、とても興味があります。
密度の濃い一日を過ごすことができ、無理をしてでもお伺いして、本当に良かったと思います。ただ、問題が一点……。先生方のお話があまりにも面白く、身体の感度を上げすぎてしまい、そのあとが大変でした・・・。身体的速度が意識的速度を上回り、山形に帰ってきてから丸一日、身体と意識の速度を合わせるのに一苦労したのです。俗世は身体の速度を落とさなければ、生きていけないのですねェ……。
さて、今回のお手紙では、「この日の学校」で甲野先生がちらっとおっしゃられた「STAP細胞騒動」についての私見を、述べさせていただきたいと存じます。(長くなってしまったので、前後編に分けて、お送りいたします)。
◇STAP細胞騒動についての私見
この騒動を、"一般"(私は、この言いかたが、嫌いですが!)の人から見ると、「科学」が異常に見えるのかもしれません。
"本人が「作った」というのなら、やらせてみればいい。あとは、何をいう訳でもなくいいのではないか? ルールがどうの、と騒ぎすぎではないか?"
そう感じる人が、いらっしゃると思います。
正直に申し上げれば、「作ってもらう」以外に「解決」はあり得ないでしょう。実は、"科学者"もそう思っていると思います。あるなら、作る。作れるなら、ある。
では、どこに"一般"の人と、"科学者"との「意見」の違いが生まれるのでしょう?
なぜ、"科学者"がルールにこだわるように見えるのでしょう?
私もかなり悩みました。悩んでおります。悩み、続けて、おります。悩んでいる過程として、ここで、4月10日に、フェイスブックに投稿した文章をひいてみます。
2014年4月10日
新聞もテレビもないので、ネットのかなり偏った情報しか得ていないけれど、小保方さんの疑惑から波及して、「科学倫理の徹底」をする流れになっている。
しかし、大きな懸念は、多くの大学・研究機関が、「お金で」「効率的に」「全体的に」この問題を解決しようとするだろうなぁ、ということだ。
N=1で申し訳ないが、自分が科学的思考法・表現方法の訓練を受けているときを振り返ってみよう。私が、科学倫理を初めて「実感」したのは、指導教官との莫大な時間をかけた議論の積み重ねがあったからだ。その「実感」も、まだまだ弱弱しいものである。自分のデータを持ち、論文を批判的に読み進め、他の研究者の人たちと何度も会い議論することで、その「実感」を強めていくものだろうと、思う。
私たちにとって、当たり前のことは「当たり前」すぎて気づきにくいが、「当たり前」を習うことは、実は非常に時間がかかることである。私たちは、子どもの頃のことを簡単に忘れる。お辞儀をする当たり前、挨拶をする当たり前、お箸を使う当たり前、日常の中で繰り返され、息を吸い、吐くかのごとく身体に身に着けることで、ようやく「当たり前」になる。
泳ぐことに卓越しているアザラシが、水に入ってすぐに泳げるだろうか? いや、彼らだって、長い時間をかけて、体得していくのである。
今回の問題の深さは、科学の「当たり前」が彼女にとっては「当たり前」と認識されていないことにあると思う(そして、「かわいそうだ」「一生懸命やっている」という理由で、彼女を擁護する多くの人にとっても認識はされていないのだろう)。
行政や、大学職員が、「当たり前」を「当たり前」として認識せず、「何分間の講義を必須とする」ことや、「レポートのコピペを厳しく罰する」ことで、効率よく「科学的倫理に則った人間」が生産できると、この問題を受けてなお、考えないだろうか?
科学倫理だって、「倫理」なのだから、生き方、もっと言えば生き様を学ぶことである。たった何回かの、何分かの、「授業」や「レポート」で生き様を学ばせるといったら、笑われることではないだろうか?
「時間をかけて」「非効率を恐れず」「個別的に」この問題にあたる流れに、なっていくことを、願うばかりである。
上記の文章の中での肝は、「科学者にとって、論文のルールを守ることは、息をするように"当たり前"のことである」という考え方です(なぜ"当たり前"かは、後述します)。
私は、先生のおっしゃった「科学が職人的世界からズレている」というお言葉にずっとひっかかりを覚えています。私の中では、科学者は、まごうことなき職人だからです。
どんな職人か?
それは、「あまねく人々に通じる事実記載を行うこと」の職人です。
まだ、研究室に入りたての頃、いい加減な記述をした際に、指導教官にたしなめられた記憶が、私にとっては今でも宝物と言えるでしょう。
「科学者は、言葉を使ってメシを食べています。言葉のプロなのです。だから、名詞の一つ一つ、動詞の一つ一つ、助詞の一つ一つ、隅々にまで、気を配らなければなりません。"解釈はこれしか許されない"という書き方を、自分が確かに見た事実と、突き合わせなければなりません」
イメージと違うでしょうか?科学者は、試験管を振ることでも、顕微鏡を覗くことでも、解剖をすることでもなく、言葉を用いることが仕事だと、言われたのです(もちろん、手を動かすことは"前提"ですが)。
言葉を厳格に用いて、「誰がいつやっても、同じ結果を得られるように、同じ解釈を得られるように」事実を記載していくことが、仕事の本質なのです。
彼女は、小保方さんは、悪意があれ、なかれ、その「職人仕事」を放棄しました。
なぜでしょう?
◇「世界」を知りたいのか?「世界」を知った私を知ってほしいのか?
私は、STAP騒動を初めて知った時に、彼女が「世界を知りたい」と思って科学をしているのだろうか? ということに、まず引っかかりました。
誰よりも早く、世界の秘密をこっそりと覗いてみたい……。
好奇心、知的欲求、知的衝動が動機ならば、「見易さ」や「データの齟齬」は、実はとるに足らない問題なはずです。なぜならば、自分の見たものこそが、その姿こそが、「世界」だからです。「世界」の姿、間違いのない「自然」だからです。「世界」を表すことを、偽ることはありません。「私は、世界で一番最初にこんな世界を覗きました!」堂々としていればよいのです
おそらく、彼女は、主体を「自分」においてしまった。もっといえば、「世間から見られる自分」においてしまった。ありのままの「世界」の方ではなく、こうであったらいい、という「幻想」に、主軸を置いてしまった。
小保方さんの言動を眺めていると、
科学は、生き方だと思うのですが……。いつの間にか、道具になりさがってしまいました。
◇二律背反を生きるための、科学
「科学的」という言葉を使う人間が跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)し始めて、どれぐらいたったでしょうか?定量的に扱えることが「科学的」であって、「世界」を正しく記述し、「感覚的」なものは排除してしかるべきである。
しかし、「科学的」=「定量的」でしょうか? 「定量的」ならば、「世界」を正しく記述できるのでしょうか?
違います。違います。違います。
真に「科学的」とは、「世界を記述しきれていない」という負い目を、必ず背負っているものです。
「私は、知りたい。そして、世界の秘密を垣間見た。しかし、"それそのもの"を表すことば、ない。どれだけことばを尽くしても、私は"世界"を表し切れない。ことばは、それ、そのものには、遠く及ばない。」
「だが、それでも、私は知る行為を、止めることができない。」
一様に"科学"に対する姿勢を規定するつもりはありません(それこそ非科学的態度でしょう)。私は、"科学"には常に「世界を知りたいのに知りきれない。伝えたいのに伝えきれない」という、二律背反が潜んでいると思います。
「世界には、必ず真理(世界を記述するもの)がある。」
おお、なんという、自己矛盾!!二律背反!!
論文の形式は「序論・方法・結果・考察」をとることが標準的です。
序論:「これまでこういうことが分かっていて、こういうことが分かっていなかった」
論文の最後は、基本的には「こういうことがまだ解らない」という言葉で結ばれます。
研究を行っても、「まだ、解らない」ことがたくさんあることを、自覚するのです。解るためにやって、それでも出てくるのは、「まだ、解らない」。
「知りたい。知れない。知りつくせない。それでも、進むしかない」という逡巡の足跡が、科学だと、私は思うのです。
先生は、小保方騒動に、足跡を、見出しましたか? 私には、ただの政治ゲームにしか、映りませんでした。
◇科学という名の宗教
科学は、宗教です。もうちょっと正確に言えば、宗教に近い構造を持っている。
「世界を量で表し、定式化することができる」
一つの教義は、上記に示した通りです。意識的に、無意識的に、科学者は上記の教義を頭に入れなければなりません。
そうして、研究に励む。だって、「定式化できる」と思えなければ、研究などやっていけません。
しかし、この、科学≒宗教という考え方はあまり人に支持されたことがありません。「何をバカなことをいっているんだ!?」「宗教のインチキを暴いたのが科学だろう?」「正反対のものじゃないのか?」「宗教なんて、気持ち悪いものと一緒にするなよ」。
うーん、不評の嵐。
でも、
「世界は○○で説明できる」
○○に、好きな神様の名前を入れてみましょう。これのどこが、宗教と違うのでしょうか?
科学は人間に力を与えました。科学で明らかにされたことが、科学技術となり、ますます威光は強くなりました("科学"と"科学技術"の違いに関しては、日照雨以前のお手紙のやりとりの二回目にちらっと書きました。併せてご参考ください)。
「世界は、科学技術によって操作できる。科学技術を信じなさい。そして、その基になっている科学を信じなさい」
科学技術の力が高まり、"科学様"の力が増してきました。ああ、"科学様"、悩める私たちをお救いください。
◇科学の二つ目の教義
しかし、科学は宗教と異なります。私は、ただ一点、宗教と異なる点を見つけ出しました。それは、「疑うこと」です。
科学は、永遠に「疑うこと」でようやく成り立てる。宗教は、永遠に「信じること」で成り立ち始めるのに対して。
「科学」が「科学」足り得るためには、「疑い」がなければなりません。「物が落ちるのは、万有引力のせいである」。これを、頭から信じるのではなく、「万有引力とはなにか?」「どこまで適用されるものなのか?」「力を伝えるモノは何か?」……。疑い続けなければなりません。
ともすれば、万能な科学は、ときに神様たり得ます。天候を予測し、人間を超越し、時を超えられる。でも、たった一つ、「それって本当?」と言える権利を、疑い続ける権利を、科学は保障してくれます。再現性の確保、その一点で、ようやく宗教を脱することができています。自分の身体と、頭で、考える権利と手段を、用意してくれているのです。
最近、この「疑うこと」の教義が、ごっそりと、抜けているように思います。
例えば、サイエンスコミュニケーターに、私は違和感を覚えつづけています。最近少しずつサイエンスコミュニケーター、という職業が認知されてきました。博物館、科学館、大学などで、「科学」を「科学になじみのない人」に伝えること、を職とする人たちのことです。科学に携わる人が、研究者以外にも、とうとう出てきたのです。私も「そういう仕事で飯が食えるなら、楽しそうだな」と憧れを抱いています。しかし、どうも私は、初めて知ったときからずっと「サイエンスコミュニケーター」というものに、違和感を覚えています。
しかし、この前、友人と話していて、自分が「サイエンスコミュニケーター」に違和感を覚えていた原因がはっと、分かりました。少なくとも、私が受けてきた中で「自分が間違っているかもしれない」というスタンスで話しているものはなかったのです。
「科学」は考え方・姿勢です。「自分の観測したもの、自分の考えが間違っているかもしれない」と常に傍らに「疑うコト」を置くことだと、思います。コミュニケーション、というものが「双方的」であることを鑑みれば、思想を一緒に考える、というのが「コミュニケーション」でしょう。
「こういう科学的事実があってですね……」と確認された事実を伝える"だけ"では「昔キリストという人が一回死んだけど復活してですね……」というのとやはりあまり変わりがないのはないでしょうか?
結局、「科学的な事実(もしくはその面白さ)を広げたい」というのは、「サイエンス・コマーシャル」というべきなのです。企業は「哲学」を売り出すのではなく、「どれだけこれが良い商品か」を前面に出す。「サイエンスコミュニケーション」が「科学が解明した事実を分かりやすく市民(笑)に伝える」だけならば、「うちの科学はこんなにすごい!」ってことを宣伝するだけになってしまいます。
「communication for science」(科学の"ための"コミュニケーション)なのか
◇「科学社会」となって
科学を宗教とみなすと、現代には、「サイエンスコミュニケーター」という、布教者、神父様が出始めているのです。
昔は、選ばれた人々、「世界」と交信できる天賦の才と術をもった人だけの特権であった「科学者」という特殊職業人がいました。研究所という教会の奥底に潜み、ひっそりと「世界」と格闘し、そしてひっそりと、次にバトンを渡していました。
しかし、「科学者」の格闘が、だんだんと"市民"にも影響を与えるようになりました。教えは、教会から引っ張り出され、特権階級は崩されてきています。
湯川秀樹、梅棹忠夫は、この「科学社会」について、こんな風に述べていました。
(梅棹)大変ルーティン化し、大衆化した科学の時代が目前に迫っている。そんなことがいえませんか。とくに、アメリカ、ソ連、日本では、人類史上初めての「科学社会」へ接近しつつある。人間がいままでつくってきた、これまでのさまざまな社会形態の中には見られない、科学が支配する社会。初めて、徹底的影響力をもって、科学が君臨する社会に近づきつつあるということ。それは中世において、宗教がすべてを支配していた社会にだいたい対比できる。いや、科学社会がはらんでいる問題をもうちょっと考えると、宗教が一番勢威をふるった時代とは必ずしも対比できないかもしれない。一種の中世後期の状態と考えた方がいいかもしれない。つまり、いまやわれわれの社会が向かいつつある時代は、十九世紀からはっきりと方向づけられた科学の時代の「後期」なんだ、と考えた方がいいかもしれません。科学の爛熟期に入りつつあるといってもいいでしょう。いわば刈取りの行われている時期なんだ――ここで、それこそ時代の一つの完結が行われる。科学において完結する社会、科学によって一応つじつまの合った社会が出現しつつあるのかもしれない、ということです。
しかし、もしそうとすると、これは一つの破綻を前提にしているようなものです。
「疑うコト」を忘れ、支配的になった科学は、どうなるでしょうか?ちなみに、上記の湯川・梅棹対談は、1966年ごろに行なわれています。約50年前ですね。「科学社会後期」はもうすぐ終焉となるでしょうか?
長くなってまいりました。次回、後編では「なぜ、論文のルールにこだわるのか?」ということと、「科学システムの危うさ」、そして、「科学が今後どうなっていくのか」を考えていきたいと思います。
季節の変わり目になり、急激に暑くなってまいりました。どうぞ、お体にお気をつけてください。
取り急ぎ、失礼いたします。
福岡 要
文章の内容は、本筋とは異なるかもしれませんが、まず私が何を感じたのかをお見せしたいと思います。
今晩、ブックトークで「人間にとって科学とはなにか」(湯川・梅棹 中公クラシックス)について熱く語ったからかもしれない。どうにも、つぶやかなくては気が済まない。
(例えば、http://sankei.jp.msn.com/science/news/140507/scn14050713070001-n1.htm)
「世界」の姿をどうやってとらえて考えていくか、ではなく、「自分の考えた仮説」に、「世界」の姿をどうやって合わせるか、に重点が置かれてしまった(ように傍からは見えますが、本当のところは分かりません。個人の世界観に踏み込んで言及することは難しいですね)。
同時に、
「世界を記述しきるのは不可能である。」
方法:「そこで、私は分かっていないことに対してこのような方法で挑んだ」
結果:「その結果、事実としてこのようなものを発見しました」
考察:「この事実は、こう解釈できる。しかし、いまだにこういうことが解らない」
「communication via science」(科学を"通じた"コミュニケーション)なのか、
「サイエンスコミュニケーション」にはその哲学が欠けているかもしれません。
中世において比類のない支配体系を数世紀にわたって維持しつづけた宗教社会が崩れ去って、近世への転換が行われたように、今後は、科学社会は崩壊に向う。
そして、科学を乗り越えるというか、科学以外のものが支配権を握るようになる、ということが考えられるのではないでしょうか。科学というものがすでに後期的状態に入っているということです。
(湯川秀樹・梅棹忠夫『人間にとって科学とはなにか』中公クラシックス、p150)
福岡要氏プロフィール
1988年、東京生まれ。北海道大学生命科学院修士課程卒業。行動生態学、神経行動学専攻。研究テーマは「カラスの遊び行動」。「人間とは何か?」を科学・宗教・芸術という枠にとらわれず、見極めていきたい。山形県在住。
以上1日分/掲載日 平成26年6月21日(土)