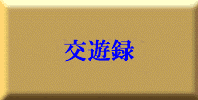 |
'01 1寧 2寧 3寧 4寧 5寧 6寧 7寧 8寧 9寧 10寧 11寧 12寧 '00 1寧 2寧 3寧 4寧 5寧 6寧 7寧 8寧 9寧 10寧 11寧 12寧 '99 1寧 2寧 3寧 4寧 5寧 6寧 7寧 8寧 9寧 10寧 11寧 12寧 |
俀侽侽侽擭俉寧俈擔乮寧乯
挬丄娸榓揷偺堦怷廏晇巵偐傜揹榖丅梡審偼丄巹偑愭擔擖庤傪埶棅偟偰偍偄偨崌嬥岺嬶峾偺俽俲俽係俁丄係係偵偮偄偰偺悢検摍偺妋擣偩偭偨丅俽俲俽係俁偼扽慺峾偵彫検僶僫僕僂儉偑揧壛偝傟偨懳徴寕梡崌嬥岺嬶峾偱丄鑧娾婡偺僺僗僩儞偵梡偄傜傟傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅
偙傟偼巹偑怣廈偺峕嶈媊枻巵偲偄傠偄傠庤棤寱偺峾嵽偵偮偄偰憡択偟尋媶偟偨寢壥丄偦偺峝偝偲忎晇偝偐傜偄偭偰偐側傝偺憿傝偵偔偝偼偁傞傕偺偺丄旕忢偵忎晇偩偑偨偄傊傫憿傝偵偔偄儅儗乕僕儞僌峾乮挻嫮椡峾倄俙俧乯埲奜偱偼嵟傕岦偄偰偄傞偲偺寢榑偵払偟偨傕偺偱偁傞丅
偦偺屻丄俽俲俽係俁傛傝嬐偐偵扽慺検偺掅偄俽俲俽係係傕帋傒丄傎偲傫偳摨偠惈擻傪帵偟偨偺偱丄俽俲俽係俁偐係係偱崱屻傕峕嶈巵偵憿偭偰傕傜偍偆偲巚偭偰偄偨栴愭丄峕嶈巵偑拲暥偟偰偄偨怣廈偺峾嵽揦偱偼俽俲俽係俁丄係係嫟偵擖庤偱偒側偔側偭偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅
偦偙偱忋栰偺壀埨峾嵽偵拲暥偟偨偑丄偙偙偱傕尒偮偐傜側偄丅偲偵偐偔帡偨傕偺偱傕丄偲庤傪恠偟偰傕傜偭偰丄傗偭偲俽俲俽俀侾偑擖庤偱偒偨偑丄俽俲俽俀侾偼僶僫僕僂儉偺懠偵僋儘儉丄僯僢働儖丄僞儞僌僗僥儞偑擖偭偰偄傞丅僯僢働儖偼擲傝偑弌傛偆偑丄僞儞僌僗僥儞偑侾亾偼偪傚偭偲婥偵擖傜側偄丅偦傟偵僯僢働儖丄僋儘儉偑擖偭偰偄傞偲從撦偟偑擄偟偔鑛偑偐偐傝偵偔偄偺偱偼側偄偐丄偲偦傟傕婥偵側傞丅
偗傟偳丄偲偵偐偔傕偺偼帋偟偱丄偦傟傪僒儞僾儖掱搙憲偭偰傕傜偆偙偲偵偟偨偲偙傠偩偭偨丅
偦偟偰偦偙傊堦怷巵偐傜偺揹榖偑擖偭偨偺偱偁傞丅偨偩堦怷巵傕俽俲俽偱峾庬巜掕偱巜掕捠傝偑尒偮偐傞壜擻惈偼敄偄偲偄偆丅乽俽俲峾偱偄偄傫偠傖側偄偱偡偐丅俇侽侽搙偱從栠偣偽廫暘擲偄偱偡傛乿偲偺偙偲丅
傑偁妋偐偵俽俲俽係俁丄係係埲奜偱傕庤棤寱梡偺峾嵽偲偟偰墿巻嶰崋傕傛偔巊偄丄偙傟偼俽俲偺俆斣偲摨偠傛偆側傕偺偩偐傜丄堦怷巵偺榖傕傢偐傞偑丄峝搙偲忎晇偝偼傗偼傝俽俲俽係俁偺曽偑堦枃傕擇枃傕忋偱偁傞丅
乽偲偵偐偔俽俲俽係俁偐係係丄偁偭偨傜偍婅偄偟傑偡傛丅俀侽倠倗偖傜偄傑偲傔偰傕攦偄傑偡偐傜乿偲棅傫偱揹榖傪抲偄偨丅揹榖傪抲偒側偑傜丄俽俲峾傪俇侽侽搙偱從栠偟偐偗傞帪偼丄彊椻偩偲從栠偟惼惈偑弌傞傫偠傖側偄偐側丄偲巚偭偨丅
偪傚偆偳慜擔丄峕嶈巵偐傜乽鑛偺偐偗曽傪俁捠傝曄偊偰傒傑偟偨丅嬶崌傪抦傜偣偰壓偝偄乿偲偺庤巻偲嫟偵俁杮偺寱偑撏偄偰偄偨偺偱丄偦偺寱傪巕嵶偵尒側偑傜丄傑偨偄傠偄傠偲峫偊偨丅
俁杮偲傕偦偺憿宍偼尒帠偵弌棃偰偄偨偑丄側偐偱傕侾杮偼傆傞偄偮偒偨偔側傞傎偳尒帠丅墶庤偐傜寱愭偵偐偗偰偺旝柇側傆偔傜傒偲丄墶庤偐傜寱怟偵偐偗偰偺棤斀傝偺嬶崌偑愨柇丅偟偽傜偔朞偐偢偵挱傔偰偄偨丅
挱傔側偑傜丄傗偭傁傝價乕僘偺僒儞僪僽儔僗僩偐偗傛偆偐丅偁傞偄偼栘恷摍偱堦搙嶬偮偗偟偰傒傛偆偐丅嵽幙偑墿巻嶰崋偩偐傜偗偭偙偆偆傑偔崟嶬偑偮偄偰偔傟傞偐傕偟傟側偄側丅偦偟偰俽俲俽俀侾偼偳傫側傆偆偵偁偑傞偩傠偆偐丄側偳偲巚偭偨傝偟偨丅
偙偆偄偆偙偲傪峫偊偰偄傞帪偼丄尰嵼偺巹偵偲偭偰偁傞庬柍忋偺帪娫丅怱傪嵡偖偙偲傗擸傒偼偄偔偮傕偁傞偑丄偙偙傑偱帺暘偑怹傟傞悽奅偑偁傞偙偲偼娫堘偄側偔崱偺巹偵偼傂偲偮偺媬偄偩傠偆丅
偦偆偄偊偽嶐擔丄偦偺寱偲嫟偵憲傜傟偰偒偨峕嶈巵偺庤巻偵傕丄俇寧偵峕嶈巵偑俀侽倣俁侽噋捈懪朄偱墦娫傪捠偟偰偐傜丄庤棤寱弍傊偺巚偄擖傟偑堦抜偲怺傑傝丄侾擔侾搙偼宮屆偡傞偐丄寱傪憿傞偐丄偦傟偵娭楢偟偨偙偲傪偟偰偄側偄偲嬛抐徢忬偑婲傝偦偆偱偡丄偲偁偭偨丅
壗帠偵偍偄偰傕忋払偡傞偵偼丄傑偢偦偺偙偲傊偐偗傞忣擬偑昁梫側偺偩傠偆丅
巹傕嵟嬤傆偲撍慠丄憱峴拞偺幵偑僄儞僗僩傪婲偡傛偆偵晲弍偺宮屆傊偺忣擬偑愗傟偰偟傑偭偨偙偲偑偁偭偨偑丄偦傫側帪偱傕偙偺庤棤寱弍偵娭偟偰偩偗偼巚偄偑徚偊偰偄側偐偭偨偐傜棫偪捈傝傕憗偐偭偨丅
恖娫丄庯枴偵偟偰傕壗偵偟偰傕丄怱偐傜懪偪崬傔傞傕偺傪帩偮偙偲偼戝帠側偙偲偐傕偟傟側偄丅
偦偆偄偊偽埲慜丄惍懱嫤夛偺栰岥桾擵愭惗偑乽傕偆婋偄偲偄偆昦恖偱傕丄錕錘偺壴偺崄傝傪妝偟傔偨傝丄壗偐帺暘偑忣擬傪孹偗偰懪偪崬傫偱偄傞傕偺傪憐偄弌偟丄偦偺帪偺妝偟偝偑慼偭偰偔傟偽彆偐傞壜擻惈偑崅偄傫偱偡傛乿偲榖偟偰壓偝偭偨偙偲偑偁偭偨丅
偙偺偙偲傪巚偄弌偟側偑傜傕丄摨帪偵傆偲摢偺嬿偵丄巹偑恖娫偲偟偰惗偒偰偄傞偙偲偺恏偝傪偐偮偰側偄傎偳崪恎偵偟傒偰帺妎偝偣傜傟偨塮夋亀傕偺偺偗昉亁傪娤偨俉寧俀俉擔偑偁偲俁廡娫偱傗偭偰偔傞側丄偲偄偆偙偲偑晜傫偱偒偨丅
崱擭偱偁傟偐傜偪傚偆偳枮俁擭丅偁偺帪惗傑傟偨愨朷姶傕俁嵥帣偵側傝丄妋幚偵巹偺屻敿惗偵塭嬁傪梌偊偰偄傞偙偲傪愜偵傆傟偰姶偠偰偄傞丅
偟偐偟丄尰偵巹帺恎偑偙偺悽偵惗傑傟偙偆偟偰懚嵼偟偰偄傞偙偲偼帠幚側偺偩偐傜丄偦偺偙偲偺堄枴傪抦傞乮偲偄偆傛傝幚姶偡傞乯偲偄偆壽戣偑傑偩巹偵偼巆偭偰偄傞偧丄偲丄偁傜偨傔偰帺暘偵尵偄暦偐偣偰偄傞丅
挬丄娸榓揷偺堦怷廏晇巵偐傜揹榖丅梡審偼丄巹偑愭擔擖庤傪埶棅偟偰偍偄偨崌嬥岺嬶峾偺俽俲俽係俁丄係係偵偮偄偰偺悢検摍偺妋擣偩偭偨丅俽俲俽係俁偼扽慺峾偵彫検僶僫僕僂儉偑揧壛偝傟偨懳徴寕梡崌嬥岺嬶峾偱丄鑧娾婡偺僺僗僩儞偵梡偄傜傟傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅
偙傟偼巹偑怣廈偺峕嶈媊枻巵偲偄傠偄傠庤棤寱偺峾嵽偵偮偄偰憡択偟尋媶偟偨寢壥丄偦偺峝偝偲忎晇偝偐傜偄偭偰偐側傝偺憿傝偵偔偝偼偁傞傕偺偺丄旕忢偵忎晇偩偑偨偄傊傫憿傝偵偔偄儅儗乕僕儞僌峾乮挻嫮椡峾倄俙俧乯埲奜偱偼嵟傕岦偄偰偄傞偲偺寢榑偵払偟偨傕偺偱偁傞丅
偦偺屻丄俽俲俽係俁傛傝嬐偐偵扽慺検偺掅偄俽俲俽係係傕帋傒丄傎偲傫偳摨偠惈擻傪帵偟偨偺偱丄俽俲俽係俁偐係係偱崱屻傕峕嶈巵偵憿偭偰傕傜偍偆偲巚偭偰偄偨栴愭丄峕嶈巵偑拲暥偟偰偄偨怣廈偺峾嵽揦偱偼俽俲俽係俁丄係係嫟偵擖庤偱偒側偔側偭偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅
偦偙偱忋栰偺壀埨峾嵽偵拲暥偟偨偑丄偙偙偱傕尒偮偐傜側偄丅偲偵偐偔帡偨傕偺偱傕丄偲庤傪恠偟偰傕傜偭偰丄傗偭偲俽俲俽俀侾偑擖庤偱偒偨偑丄俽俲俽俀侾偼僶僫僕僂儉偺懠偵僋儘儉丄僯僢働儖丄僞儞僌僗僥儞偑擖偭偰偄傞丅僯僢働儖偼擲傝偑弌傛偆偑丄僞儞僌僗僥儞偑侾亾偼偪傚偭偲婥偵擖傜側偄丅偦傟偵僯僢働儖丄僋儘儉偑擖偭偰偄傞偲從撦偟偑擄偟偔鑛偑偐偐傝偵偔偄偺偱偼側偄偐丄偲偦傟傕婥偵側傞丅
偗傟偳丄偲偵偐偔傕偺偼帋偟偱丄偦傟傪僒儞僾儖掱搙憲偭偰傕傜偆偙偲偵偟偨偲偙傠偩偭偨丅
偦偟偰偦偙傊堦怷巵偐傜偺揹榖偑擖偭偨偺偱偁傞丅偨偩堦怷巵傕俽俲俽偱峾庬巜掕偱巜掕捠傝偑尒偮偐傞壜擻惈偼敄偄偲偄偆丅乽俽俲峾偱偄偄傫偠傖側偄偱偡偐丅俇侽侽搙偱從栠偣偽廫暘擲偄偱偡傛乿偲偺偙偲丅
傑偁妋偐偵俽俲俽係俁丄係係埲奜偱傕庤棤寱梡偺峾嵽偲偟偰墿巻嶰崋傕傛偔巊偄丄偙傟偼俽俲偺俆斣偲摨偠傛偆側傕偺偩偐傜丄堦怷巵偺榖傕傢偐傞偑丄峝搙偲忎晇偝偼傗偼傝俽俲俽係俁偺曽偑堦枃傕擇枃傕忋偱偁傞丅
乽偲偵偐偔俽俲俽係俁偐係係丄偁偭偨傜偍婅偄偟傑偡傛丅俀侽倠倗偖傜偄傑偲傔偰傕攦偄傑偡偐傜乿偲棅傫偱揹榖傪抲偄偨丅揹榖傪抲偒側偑傜丄俽俲峾傪俇侽侽搙偱從栠偟偐偗傞帪偼丄彊椻偩偲從栠偟惼惈偑弌傞傫偠傖側偄偐側丄偲巚偭偨丅
偪傚偆偳慜擔丄峕嶈巵偐傜乽鑛偺偐偗曽傪俁捠傝曄偊偰傒傑偟偨丅嬶崌傪抦傜偣偰壓偝偄乿偲偺庤巻偲嫟偵俁杮偺寱偑撏偄偰偄偨偺偱丄偦偺寱傪巕嵶偵尒側偑傜丄傑偨偄傠偄傠偲峫偊偨丅
俁杮偲傕偦偺憿宍偼尒帠偵弌棃偰偄偨偑丄側偐偱傕侾杮偼傆傞偄偮偒偨偔側傞傎偳尒帠丅墶庤偐傜寱愭偵偐偗偰偺旝柇側傆偔傜傒偲丄墶庤偐傜寱怟偵偐偗偰偺棤斀傝偺嬶崌偑愨柇丅偟偽傜偔朞偐偢偵挱傔偰偄偨丅
挱傔側偑傜丄傗偭傁傝價乕僘偺僒儞僪僽儔僗僩偐偗傛偆偐丅偁傞偄偼栘恷摍偱堦搙嶬偮偗偟偰傒傛偆偐丅嵽幙偑墿巻嶰崋偩偐傜偗偭偙偆偆傑偔崟嶬偑偮偄偰偔傟傞偐傕偟傟側偄側丅偦偟偰俽俲俽俀侾偼偳傫側傆偆偵偁偑傞偩傠偆偐丄側偳偲巚偭偨傝偟偨丅
偙偆偄偆偙偲傪峫偊偰偄傞帪偼丄尰嵼偺巹偵偲偭偰偁傞庬柍忋偺帪娫丅怱傪嵡偖偙偲傗擸傒偼偄偔偮傕偁傞偑丄偙偙傑偱帺暘偑怹傟傞悽奅偑偁傞偙偲偼娫堘偄側偔崱偺巹偵偼傂偲偮偺媬偄偩傠偆丅
偦偆偄偊偽嶐擔丄偦偺寱偲嫟偵憲傜傟偰偒偨峕嶈巵偺庤巻偵傕丄俇寧偵峕嶈巵偑俀侽倣俁侽噋捈懪朄偱墦娫傪捠偟偰偐傜丄庤棤寱弍傊偺巚偄擖傟偑堦抜偲怺傑傝丄侾擔侾搙偼宮屆偡傞偐丄寱傪憿傞偐丄偦傟偵娭楢偟偨偙偲傪偟偰偄側偄偲嬛抐徢忬偑婲傝偦偆偱偡丄偲偁偭偨丅
壗帠偵偍偄偰傕忋払偡傞偵偼丄傑偢偦偺偙偲傊偐偗傞忣擬偑昁梫側偺偩傠偆丅
巹傕嵟嬤傆偲撍慠丄憱峴拞偺幵偑僄儞僗僩傪婲偡傛偆偵晲弍偺宮屆傊偺忣擬偑愗傟偰偟傑偭偨偙偲偑偁偭偨偑丄偦傫側帪偱傕偙偺庤棤寱弍偵娭偟偰偩偗偼巚偄偑徚偊偰偄側偐偭偨偐傜棫偪捈傝傕憗偐偭偨丅
恖娫丄庯枴偵偟偰傕壗偵偟偰傕丄怱偐傜懪偪崬傔傞傕偺傪帩偮偙偲偼戝帠側偙偲偐傕偟傟側偄丅
偦偆偄偊偽埲慜丄惍懱嫤夛偺栰岥桾擵愭惗偑乽傕偆婋偄偲偄偆昦恖偱傕丄錕錘偺壴偺崄傝傪妝偟傔偨傝丄壗偐帺暘偑忣擬傪孹偗偰懪偪崬傫偱偄傞傕偺傪憐偄弌偟丄偦偺帪偺妝偟偝偑慼偭偰偔傟偽彆偐傞壜擻惈偑崅偄傫偱偡傛乿偲榖偟偰壓偝偭偨偙偲偑偁偭偨丅
偙偺偙偲傪巚偄弌偟側偑傜傕丄摨帪偵傆偲摢偺嬿偵丄巹偑恖娫偲偟偰惗偒偰偄傞偙偲偺恏偝傪偐偮偰側偄傎偳崪恎偵偟傒偰帺妎偝偣傜傟偨塮夋亀傕偺偺偗昉亁傪娤偨俉寧俀俉擔偑偁偲俁廡娫偱傗偭偰偔傞側丄偲偄偆偙偲偑晜傫偱偒偨丅
崱擭偱偁傟偐傜偪傚偆偳枮俁擭丅偁偺帪惗傑傟偨愨朷姶傕俁嵥帣偵側傝丄妋幚偵巹偺屻敿惗偵塭嬁傪梌偊偰偄傞偙偲傪愜偵傆傟偰姶偠偰偄傞丅
偟偐偟丄尰偵巹帺恎偑偙偺悽偵惗傑傟偙偆偟偰懚嵼偟偰偄傞偙偲偼帠幚側偺偩偐傜丄偦偺偙偲偺堄枴傪抦傞乮偲偄偆傛傝幚姶偡傞乯偲偄偆壽戣偑傑偩巹偵偼巆偭偰偄傞偧丄偲丄偁傜偨傔偰帺暘偵尵偄暦偐偣偰偄傞丅
埲忋侾擔暘乛宖嵹擔 暯惉侾俀擭俉寧侾侾擔(嬥乯
俀侽侽侽擭俉寧侾俉擔乮嬥乯
怣廈偺峕嶈媊枻巵偵揹榖偟偨偲偙傠丄愭擔憲偭偨俽俲俽俀侾偼丄俽俲俽係俁偲偔傜傋偰抌憿偺嬶崌丄從撦偟屻偺鑛偺偐偐傝嬶崌丄從擖傟丄從栠偟屻偺擲傝偲峝搙偵偍偄偰傎偲傫偳懟怓偑側偄偲偺偙偲丅
偁傜偨傔偰婥偯偄偰傒傟偽丄俽俲俽俀侾偼恘暔梡偺峾嵽偺堦庬偱偁傞惵巻擇崋偵僶僫僕僂儉傪壛偊偨傛偆側慻惉側偺偱丄捠忢偺抌憿嶌嬈偱偼摿偵崲擄偲偄偆偙偲偼側偄偺偩傠偆丅
偙偺偲偙傠偢偭偲廳偄偙偲偽偐傝峫偊懕偗偰偄偰懱椡傕婥椡傕棊偪偰偄偨偑丄晄巚媍側傕偺偱偙偺俽俲俽俀侾偑巊偊偦偆偩偲偄偆榖傪暦偄偨偩偗偱僼僢偲娽偺慜偑彮偟柧傞偔側偭偨丅
彮偟傗傞婥偑弌偰偒偨偲偙傠偱寎偊偨梉曽偐傜偺宐斾庻偱偺宮屆偱偼壗恖傕偺恖偲庤傪岎偊偰偄傞偆偪丄偐側傝宮屆偵懪偪崬傔傞傛偆偵側傝丄敪尒丄婥偯偒傕偄偔偮偐偁偭偨丅傗偼傝懱傪捠偟偰壗偐傪峫偊偰偄傜傟傞偲偄偆偺偼桳擄偄丅
俉寧偵擖偭偰偐傜偢偭偲巹偺怱傪懆偊偰偄傞廳偄壽戣乮偦傟偑偁傑傝偵傕廳偄偨傔丄偙偙偟偽傜偔亀岎梀榐亁傪彂偄偰偄側偄偺偩偑乯偵偮偄偰傕彂偐偹偽側傜側偄偩傠偆偲巚偄丄偄傑彂偄偰偄傞丅偙傟偼丄偡偱偵嶡偟偰偄傞曽傕偁傞偩傠偆偑亀僀僔丒杒暷嵟屻偺栰惗僀儞僨傿傾儞亁傪僉僢僇働偵惗傑傟偰偒偨傕偺丅
亀傕偺偺偗昉亁偺僔儑僢僋偐傜偺俁廃擭偼丄偙偺傑傑丄偙傟傪書偊偰寎偊傞偙偲偵側傝偦偆丅
怣廈偺峕嶈媊枻巵偵揹榖偟偨偲偙傠丄愭擔憲偭偨俽俲俽俀侾偼丄俽俲俽係俁偲偔傜傋偰抌憿偺嬶崌丄從撦偟屻偺鑛偺偐偐傝嬶崌丄從擖傟丄從栠偟屻偺擲傝偲峝搙偵偍偄偰傎偲傫偳懟怓偑側偄偲偺偙偲丅
偁傜偨傔偰婥偯偄偰傒傟偽丄俽俲俽俀侾偼恘暔梡偺峾嵽偺堦庬偱偁傞惵巻擇崋偵僶僫僕僂儉傪壛偊偨傛偆側慻惉側偺偱丄捠忢偺抌憿嶌嬈偱偼摿偵崲擄偲偄偆偙偲偼側偄偺偩傠偆丅
偙偺偲偙傠偢偭偲廳偄偙偲偽偐傝峫偊懕偗偰偄偰懱椡傕婥椡傕棊偪偰偄偨偑丄晄巚媍側傕偺偱偙偺俽俲俽俀侾偑巊偊偦偆偩偲偄偆榖傪暦偄偨偩偗偱僼僢偲娽偺慜偑彮偟柧傞偔側偭偨丅
彮偟傗傞婥偑弌偰偒偨偲偙傠偱寎偊偨梉曽偐傜偺宐斾庻偱偺宮屆偱偼壗恖傕偺恖偲庤傪岎偊偰偄傞偆偪丄偐側傝宮屆偵懪偪崬傔傞傛偆偵側傝丄敪尒丄婥偯偒傕偄偔偮偐偁偭偨丅傗偼傝懱傪捠偟偰壗偐傪峫偊偰偄傜傟傞偲偄偆偺偼桳擄偄丅
俉寧偵擖偭偰偐傜偢偭偲巹偺怱傪懆偊偰偄傞廳偄壽戣乮偦傟偑偁傑傝偵傕廳偄偨傔丄偙偙偟偽傜偔亀岎梀榐亁傪彂偄偰偄側偄偺偩偑乯偵偮偄偰傕彂偐偹偽側傜側偄偩傠偆偲巚偄丄偄傑彂偄偰偄傞丅偙傟偼丄偡偱偵嶡偟偰偄傞曽傕偁傞偩傠偆偑亀僀僔丒杒暷嵟屻偺栰惗僀儞僨傿傾儞亁傪僉僢僇働偵惗傑傟偰偒偨傕偺丅
亀傕偺偺偗昉亁偺僔儑僢僋偐傜偺俁廃擭偼丄偙偺傑傑丄偙傟傪書偊偰寎偊傞偙偲偵側傝偦偆丅
埲忋侾擔暘乛宖嵹擔 暯惉侾俀擭俉寧俀侾擔(寧乯
俀侽侽侽擭俉寧侾俋擔乮搚乯
丂
傑偩弸偄擔偑偁傞偲偼偄偊丄擔偑棊偪傞偲傂偲崰傛傝壏搙偑壓偑傝丄庽忋偱偼惵徏拵偑柭偒偼偠傔偰偄傞丅
偦傫側廐偺婥攝傪姶偠傞崱擔偙偺崰偱偁傞偑丄巹偺婥帩偪偺曽偼偡偱偵梩偑傎偲傫偳棊偪偰偄傞斢廐丅
偦偆側偭偨棟桼偺嵟傕戝偒側尨場偼丄亀僀僔丒杒暷嵟屻偺僀儞僨傿傾儞亁乮娾攇彂揦摨帪戙儔僀僽儔儕乕乯傪撉傫偩偨傔偩偲巚偆丅
偙偺杮偺懚嵼偼丄側傫偲側偔侾侽擭埲忋傕慜偐傜帹偵偟偰偄偨偑丄嶐寧巓偵憽傜傟偰撉傒偼偠傔偰埲棃丄偪傚偆偳峕屗帪戙偺崏栤偺愇書偒偱偼側偄偑丄旼偺忋偵忔傞愇偺枃悢偑抜乆傆偊偰偒偨傛偆偵丄師戞師戞偵棙偒偼偠傔偰偒偨丅
僇儕僼僅儖僯傾撿晹偱愇婍帪戙偺暥壔傪偦偺傑傑堷偒偮偄偱惗偒偰偒偨儎僸懓嵟屻偺惗偒巆傝偱偁傞僀僔偑丄偦偺屒撈偱斶嶴側惗妶偵旀傟偼偰偨偺偐丄侾俋侾侾擭偺俉寧俀俋擔丄婹偊巰偵偟偦偆側巔偱丄抺嶦応偺嶒埻偄偺拞偱將偵杋偊偮偐傟偰偄偨偺偑偙偺暔岅偺偼偠傔偱偁傞丅
乽暥柧偲恑曕乿偺旤柤偺嫋偵峴傢傟偰偄偨棟晄恠側嶦滳偲敆奞偺悢乆偵傛偭偰丄儎僸懓偼僀僔埲奜慡柵偟偨偺偱偁傞丅
杮彂偺慜敿偱偼偦偺夁掱偲忬嫷傪昤偒丄屻敿偼撍慠俀侽悽婭偺暥柧幮夛偺拞偵拞擭埲屻乮偍偦傜偔俆侽嵨偡偓乯擖偭偰偒偨偙偺愇婍帪戙恖偲僇儕僼僅儖僯傾戝妛晅懏偺攷暔娰偺娭學幰偱丄怺偔偙偺愇婍帪戙恖傪垽偟偨恖乆偲偺岎棳傪捠偟偰丄偄偐偵偙偺恖暔噣僀僔噥偑弮恀側嵃偲恖偲偺懳墳偵偍偗傞婥偯偐偄丄巚偄傗傝傪帩偭偰偄偨偐傪昤偄偰偄傞丅
僀僔偑巰嫀偟丄偦偺堚懱傪夝朥偡傞偲偄偆榖偑弌偨帪丄僀僔偺嵟傕恊偟偄桭恖偱偁傝曐岇幰偺堦恖偱傕偁偭偨丄偙偺杮偺挊幰僔僆僪乕儔丒僋儘乕僶乕偺晇孨傾儖僼儗僢僪丒僋儘乕僶乕乮僇儕僼僅儖僯傾戝妛晬懏攷暔娰娰挿乯偼丄乽壢妛尋媶偺偨傔偲偐偄偆榖偑弌偨傜壢妛側傫偐將偵偱傕嬺傢傟傠丄偲丄巹偺戙傢傝偵尵偭偰傗傝側偝偄丅傢傟傢傟偼帺暘傜偺桭恖偺枴曽偱偁傝偨偄偲巚偄傑偡乿偲丄榖偟偨偲偄偆丅
傑偨丄恊桭偺侾恖偱堛巘偺僒僋僗僩儞丒億乕僾偼丄僀僔偺巰偵偮偄偰師偺傛偆側暥傪彂偄偰偄傞丅
丂
偦偺傛偆偵偟偰丄変枬嫮偔壗傕嫲傟偢偵丄傾儊儕僇嵟屻偺栰惗僀儞僨傿傾儞偼偙偺悽傪嫀偭偨丅斵偼楌巎偺堦復傪暵偠傞丅斵偼暥柧恖傪抦宐偺恑傫偩巕嫙乧摢偼偄偄偑尗偔偼側偄幰偲尒偰偄偨丅傢傟傢傟偼懡偔偺偙偲傪抦偭偨偑丄偦偺拞偺懡偔偼婾傝偱偁偭偨丅僀僔偼忢偵恀幚偱偁傞帺慠傪抦偭偰偄偨丅斵偺惈奿偼塱墦偵懕偔傕偺偱偁偭偨丅恊愗偱丄桬婥偑偁傝丄帺惂怱傕嫮偐偭偨丅偦偟偰斵偼偡傋偰傪扗傢傟偨偵傕峉傢傜偢丄偦偺怱偵偼偆傜傒偼側偐偭偨丅斵偺嵃偼巕嫙偺偦傟偱偁傝丄斵偺惛恄偼揘妛幰偺偦傟偱偁偭偨丅
偙偙偵弎傋傜傟偰偄傞傛偆偵僀僔乮偙偺柤慜傕杮恖偑晹懓偺潀偵廬偭偰偐丄杮柤傪柤忔傜側偐偭偨偨傔僋儘乕僶乕娰挿偑柤晅偗偨偺偱偁傞乯偼丄暥柧幮夛偑巒傑偭偨埲屻偺恖娫偑丄摿暿側廋嬈偵傛偭偰杹偄偨恖奿傛傝傕傕偭偲僫僠儏儔儖側懠偺懡偔偺柉懓偺恖乆偵偲偭偰傕嫟姶偱偒傞恖偲偟偰偺悢乆偺旤幙傪旛偊偰偄偨傛偆偱偁傞丅
偦偺婥偯偐偄偺傗偝偟偝偲怺偝偼丄僀僔偑偁傞掱搙塸岅傪榖偣傞傛偆偵側偭偰偐傜偱傕丄暿傟偵椪傫偱暿傟偺尵梩傪僴僢僉儕偲尵偆偙偲偵偼鏢鏞偑偁傝丄嫀偭偰峴偔恖偵偼偝傝偘側偔乽傕偆峴偔偺丠乿偲尵偄丄媡偵帺暘偑偦偺応傪棧傟傞帪偼乽偁側偨偼嫃側偝偄丄傏偔偼峴偔乿偲偄偆昞尰傪岲傫偩偙偲偵傕尰傟偰偄傞丅
偙偺杮偵傛偭偰丄巹偼恖娫偑擾峩傪巒傔偨偲偄偆偙偲帺懱偵傕壗偲傕尵偄條偺側偄偆偟傠傔偨偝傪柧妋偵姶偠傞傛偆偵側偭偰偟傑偭偨丅
偐偭偰乽擾偼崙偺婎乿側偳偲尵偄奐崵偡傞偙偲偵惓媊偲巊柦姶傪姶偠偰偄偨帪戙偺恖偑偆傜傗傑偟偔丄摨帪偵嬸偐偝偲忣偗側偝偺敽偭偨偠偮偵暋嶨側姶忣偺僇僋僥儖偱姶偠傜傟傞丅
偙偆偄偆偙偲傪峫偊傞傛偆偵側偭偨偺傕帪戙偑恑傒丄恖娫偺娐嫬攋夡傗恖怱峳攑偑杮摉偵怺崗側抜奒偵擖偭偨偐傜偩偲巚偆丅
傕偭偲傕巹偵偼梒偐偭偨崰偐傜丄帺慠娐嫬偺攋夡偵懳偡傞斶偟傒偲搟傝偑夎惗偊偰偄偰丄彫妛峑偺掅妛擭偺崰偐傜戭抧憿惉偱栘偑敯傜傟嶳偑嶍傜傟偰備偔偙偲傪扱偔嶌暥傪彂偄偰偄偨丅
偨偩丄晛捠偦偆偄偆巚偄偼擭楊傪廳偹傞偛偲偵敄傜偄偱丄尰幚惗妶傊偺娭怱偺曽偑嫮偔側傞偲偄偆偑丄巹偺応崌偼惛恄擭楊偺戅峴尰徾偑婲偒偰偄傞偺偐丄俁擭慜丄塮夋亀傕偺偺偗昉亁傪娤偰偐偮偰側偄僔儑僢僋傪庴偗偰埲棃丄抜乆偲恖娫偑暥柧偲偐暥壔丄壢妛偺旤柤偺傕偲偵峴側偭偰偒偨偝傑偞傑側強峴偵懳偟偰崻杮揑側媈榝偑晜偒弌偟偰偒偰偟傑偄丄偦偙偵俀侽戙偺弶傔揗傟傞傛偆偵偟偰撉傫偩丄恖抭偺愺偼偐偝傪歰偄帺慠悘弴傪愢偔亀憫巕亁傑偱巚偄弌偟偰偟傑偭偨偐傜丄崱屻巹偑偳偺傛偆側婳愓傪巆偟偰惗偒偰備偔偺偐丄変偑偛偲側偑傜曫慠偲偣偞傞傪摼側偄丅
偨偩丄俈擔偺亀岎梀榐亁偺嵟屻偵傕彂偄偨偑丄巹偑崱偵側偭偰偳偆峫偊傛偆偲丄巹偲偄偆懚嵼偑偄傑偙偺悽偵惗偒偰嵼傞偙偲偼暣傟傕側偄帠幚側偺偩偐傜丄偦偙傪揙掙偟偰傒偮傔傞偙偲偟偐側偄偺偐傕偟傟側偄丅
丂
傑偩弸偄擔偑偁傞偲偼偄偊丄擔偑棊偪傞偲傂偲崰傛傝壏搙偑壓偑傝丄庽忋偱偼惵徏拵偑柭偒偼偠傔偰偄傞丅
偦傫側廐偺婥攝傪姶偠傞崱擔偙偺崰偱偁傞偑丄巹偺婥帩偪偺曽偼偡偱偵梩偑傎偲傫偳棊偪偰偄傞斢廐丅
偦偆側偭偨棟桼偺嵟傕戝偒側尨場偼丄亀僀僔丒杒暷嵟屻偺僀儞僨傿傾儞亁乮娾攇彂揦摨帪戙儔僀僽儔儕乕乯傪撉傫偩偨傔偩偲巚偆丅
偙偺杮偺懚嵼偼丄側傫偲側偔侾侽擭埲忋傕慜偐傜帹偵偟偰偄偨偑丄嶐寧巓偵憽傜傟偰撉傒偼偠傔偰埲棃丄偪傚偆偳峕屗帪戙偺崏栤偺愇書偒偱偼側偄偑丄旼偺忋偵忔傞愇偺枃悢偑抜乆傆偊偰偒偨傛偆偵丄師戞師戞偵棙偒偼偠傔偰偒偨丅
僇儕僼僅儖僯傾撿晹偱愇婍帪戙偺暥壔傪偦偺傑傑堷偒偮偄偱惗偒偰偒偨儎僸懓嵟屻偺惗偒巆傝偱偁傞僀僔偑丄偦偺屒撈偱斶嶴側惗妶偵旀傟偼偰偨偺偐丄侾俋侾侾擭偺俉寧俀俋擔丄婹偊巰偵偟偦偆側巔偱丄抺嶦応偺嶒埻偄偺拞偱將偵杋偊偮偐傟偰偄偨偺偑偙偺暔岅偺偼偠傔偱偁傞丅
乽暥柧偲恑曕乿偺旤柤偺嫋偵峴傢傟偰偄偨棟晄恠側嶦滳偲敆奞偺悢乆偵傛偭偰丄儎僸懓偼僀僔埲奜慡柵偟偨偺偱偁傞丅
杮彂偺慜敿偱偼偦偺夁掱偲忬嫷傪昤偒丄屻敿偼撍慠俀侽悽婭偺暥柧幮夛偺拞偵拞擭埲屻乮偍偦傜偔俆侽嵨偡偓乯擖偭偰偒偨偙偺愇婍帪戙恖偲僇儕僼僅儖僯傾戝妛晅懏偺攷暔娰偺娭學幰偱丄怺偔偙偺愇婍帪戙恖傪垽偟偨恖乆偲偺岎棳傪捠偟偰丄偄偐偵偙偺恖暔噣僀僔噥偑弮恀側嵃偲恖偲偺懳墳偵偍偗傞婥偯偐偄丄巚偄傗傝傪帩偭偰偄偨偐傪昤偄偰偄傞丅
僀僔偑巰嫀偟丄偦偺堚懱傪夝朥偡傞偲偄偆榖偑弌偨帪丄僀僔偺嵟傕恊偟偄桭恖偱偁傝曐岇幰偺堦恖偱傕偁偭偨丄偙偺杮偺挊幰僔僆僪乕儔丒僋儘乕僶乕偺晇孨傾儖僼儗僢僪丒僋儘乕僶乕乮僇儕僼僅儖僯傾戝妛晬懏攷暔娰娰挿乯偼丄乽壢妛尋媶偺偨傔偲偐偄偆榖偑弌偨傜壢妛側傫偐將偵偱傕嬺傢傟傠丄偲丄巹偺戙傢傝偵尵偭偰傗傝側偝偄丅傢傟傢傟偼帺暘傜偺桭恖偺枴曽偱偁傝偨偄偲巚偄傑偡乿偲丄榖偟偨偲偄偆丅
傑偨丄恊桭偺侾恖偱堛巘偺僒僋僗僩儞丒億乕僾偼丄僀僔偺巰偵偮偄偰師偺傛偆側暥傪彂偄偰偄傞丅
丂
偦偺傛偆偵偟偰丄変枬嫮偔壗傕嫲傟偢偵丄傾儊儕僇嵟屻偺栰惗僀儞僨傿傾儞偼偙偺悽傪嫀偭偨丅斵偼楌巎偺堦復傪暵偠傞丅斵偼暥柧恖傪抦宐偺恑傫偩巕嫙乧摢偼偄偄偑尗偔偼側偄幰偲尒偰偄偨丅傢傟傢傟偼懡偔偺偙偲傪抦偭偨偑丄偦偺拞偺懡偔偼婾傝偱偁偭偨丅僀僔偼忢偵恀幚偱偁傞帺慠傪抦偭偰偄偨丅斵偺惈奿偼塱墦偵懕偔傕偺偱偁偭偨丅恊愗偱丄桬婥偑偁傝丄帺惂怱傕嫮偐偭偨丅偦偟偰斵偼偡傋偰傪扗傢傟偨偵傕峉傢傜偢丄偦偺怱偵偼偆傜傒偼側偐偭偨丅斵偺嵃偼巕嫙偺偦傟偱偁傝丄斵偺惛恄偼揘妛幰偺偦傟偱偁偭偨丅
偙偙偵弎傋傜傟偰偄傞傛偆偵僀僔乮偙偺柤慜傕杮恖偑晹懓偺潀偵廬偭偰偐丄杮柤傪柤忔傜側偐偭偨偨傔僋儘乕僶乕娰挿偑柤晅偗偨偺偱偁傞乯偼丄暥柧幮夛偑巒傑偭偨埲屻偺恖娫偑丄摿暿側廋嬈偵傛偭偰杹偄偨恖奿傛傝傕傕偭偲僫僠儏儔儖側懠偺懡偔偺柉懓偺恖乆偵偲偭偰傕嫟姶偱偒傞恖偲偟偰偺悢乆偺旤幙傪旛偊偰偄偨傛偆偱偁傞丅
偦偺婥偯偐偄偺傗偝偟偝偲怺偝偼丄僀僔偑偁傞掱搙塸岅傪榖偣傞傛偆偵側偭偰偐傜偱傕丄暿傟偵椪傫偱暿傟偺尵梩傪僴僢僉儕偲尵偆偙偲偵偼鏢鏞偑偁傝丄嫀偭偰峴偔恖偵偼偝傝偘側偔乽傕偆峴偔偺丠乿偲尵偄丄媡偵帺暘偑偦偺応傪棧傟傞帪偼乽偁側偨偼嫃側偝偄丄傏偔偼峴偔乿偲偄偆昞尰傪岲傫偩偙偲偵傕尰傟偰偄傞丅
偙偺杮偵傛偭偰丄巹偼恖娫偑擾峩傪巒傔偨偲偄偆偙偲帺懱偵傕壗偲傕尵偄條偺側偄偆偟傠傔偨偝傪柧妋偵姶偠傞傛偆偵側偭偰偟傑偭偨丅
偐偭偰乽擾偼崙偺婎乿側偳偲尵偄奐崵偡傞偙偲偵惓媊偲巊柦姶傪姶偠偰偄偨帪戙偺恖偑偆傜傗傑偟偔丄摨帪偵嬸偐偝偲忣偗側偝偺敽偭偨偠偮偵暋嶨側姶忣偺僇僋僥儖偱姶偠傜傟傞丅
偙偆偄偆偙偲傪峫偊傞傛偆偵側偭偨偺傕帪戙偑恑傒丄恖娫偺娐嫬攋夡傗恖怱峳攑偑杮摉偵怺崗側抜奒偵擖偭偨偐傜偩偲巚偆丅
傕偭偲傕巹偵偼梒偐偭偨崰偐傜丄帺慠娐嫬偺攋夡偵懳偡傞斶偟傒偲搟傝偑夎惗偊偰偄偰丄彫妛峑偺掅妛擭偺崰偐傜戭抧憿惉偱栘偑敯傜傟嶳偑嶍傜傟偰備偔偙偲傪扱偔嶌暥傪彂偄偰偄偨丅
偨偩丄晛捠偦偆偄偆巚偄偼擭楊傪廳偹傞偛偲偵敄傜偄偱丄尰幚惗妶傊偺娭怱偺曽偑嫮偔側傞偲偄偆偑丄巹偺応崌偼惛恄擭楊偺戅峴尰徾偑婲偒偰偄傞偺偐丄俁擭慜丄塮夋亀傕偺偺偗昉亁傪娤偰偐偮偰側偄僔儑僢僋傪庴偗偰埲棃丄抜乆偲恖娫偑暥柧偲偐暥壔丄壢妛偺旤柤偺傕偲偵峴側偭偰偒偨偝傑偞傑側強峴偵懳偟偰崻杮揑側媈榝偑晜偒弌偟偰偒偰偟傑偄丄偦偙偵俀侽戙偺弶傔揗傟傞傛偆偵偟偰撉傫偩丄恖抭偺愺偼偐偝傪歰偄帺慠悘弴傪愢偔亀憫巕亁傑偱巚偄弌偟偰偟傑偭偨偐傜丄崱屻巹偑偳偺傛偆側婳愓傪巆偟偰惗偒偰備偔偺偐丄変偑偛偲側偑傜曫慠偲偣偞傞傪摼側偄丅
偨偩丄俈擔偺亀岎梀榐亁偺嵟屻偵傕彂偄偨偑丄巹偑崱偵側偭偰偳偆峫偊傛偆偲丄巹偲偄偆懚嵼偑偄傑偙偺悽偵惗偒偰嵼傞偙偲偼暣傟傕側偄帠幚側偺偩偐傜丄偦偙傪揙掙偟偰傒偮傔傞偙偲偟偐側偄偺偐傕偟傟側偄丅
埲忋侾擔暘乛宖嵹擔 暯惉侾俀擭俉寧俀俀擔(壩乯
俀侽侽侽擭俉寧俀俀擔乮壩乯
愨朷偟偰偄傞帪偼愨朷偺乽寎庰乿偑棙偔傜偟偄丅
嶐栭丄媣偟傇傝偵戝嶃偺惛恄壢堛 柤墇峃暥巵偲揹榖偱榖偟丄崱擔偼傗偼傝媣偟傇傝偵丄幮抍朄恖惍懱嫤夛丒恎懱嫵堢尋媶強偺栰岥桾擵愭惗偵偍夛偄偟偰丄偮偔偯偔偲朻摢偺尵梩偑嫻拞偵晜偐傃忋偑偭偰偒偨丅
柤墇巵偵偮偄偰偼丄偙偺儂乕儉儁乕僕偲儕儞僋偟偰偄傞亀柤墇僨傿傾儘乕僌亁偺亀擔婰偺傛偆側恖惗亁傪撉傫偱偄偨偩偗傟偽傢偐傞偲巚偆偑丄僶儕搰偱惛恄揑戝寖恔偵尒晳傟偨傛偆偱丄偦偺捈屻偺俉寧侾侽擔丄僶儕搰偐傜巹偵揹榖偑偁偭偨偑丄偦偺屻偢偭偲梋恔偑懕偄偰偄偨傜偟偔丄嶐擔傑偱楢棈偑側偐偭偨偺偱偁傞丅傕偭偲傕巹偺曽傕偢偭偲愨朷偺掙偵偄偨偐傜丄偁偊偰偙偪傜偐傜傕揹榖傪偟側偐偭偨丅
傕偪傠傫婥偵偼偐偐偭偰偄偨偑丄埲慜傕壗搙偐惛恄忬懺偑晄巚媍偲儕儞僋偟偰偄偨偐傜丄側傫偲側偔柤墇巵傕恏偄忬嫷偩傠偆偲偼巚偭偰偄偨丅偦偟偰埬偺掕丄嶐擔偺揹榖偺條巕偱偼丄乽扤偲傕嫟桳偟偨偄偲巚傢側偄偟偐傕懢屆偺愄偐傜偢偭偲偦偙偵偁偭偨傛偆側愨朷姶乿偵曪傑傟丄姶忣偺晜偒捑傒偺拞偱丄帺傜偺惛恄傪嵹偣偨彫慏傪偳偆偟傛偆傕側偔偝傑傛偭偰偄偨傜偟偄丅偟偐偟丄峫偊偰傒傟偽偙傟傎偳懡偔偺帠審偑婲偒丄壙抣娤偑崿撟偲偟偰偒偰偄傞側偐偱丄偟偐傕偦傟傜偵嵟傕東楳偝傟偰偄傞恖払偺榖傪暦偔偲偄偆怑嬈偱丄恖娫側傜傆傝傑傢偝傟側偄敜偑側偄乮帺暘偺姶妎傪撦傜偣丄宍偳偍傝偺幙栤傪偟偰丄偨偩婡夿揑偵栻傪弌偡偩偗偺惛恄壢堛側傜塭嬁傪庴偗傞偙偲傕側偄偐傕偟傟側偄偑乯丅
徻偟偄榖偼傑偩暦偄偰側偄偑乮傕偭偲傕偦傟偑偆傑偔尵梩偵側傞偐偳偆偐傕傢偐傜側偄偑乯丄柤墇巵偺係侽擭嬤偔偺恖惗偺側偐偱旕忢偵戝偒側愡栚傪寎偊偰偄傞傛偆偩丅
偦偟偰崱擔丄惍懱嫤夛偱栰岥桾擵愭惗偲俆儢寧傇傝偵偍夛偄偡傞丅
偄傑傑偱悢廫夞偍夛偄偟偰丄忢偵偦偺巚嶕偺怺偝偲姶惈偺塻偝偵僞儊懅傪偮偐偣懕偗傜傟偰偒偨偑丄崱夞傕儂僩儂僩姶扱丅
偙傟傎偳偺揤嵥偵側傞偲丄偄偭偨偄廫暘偵榖偺庴偗傪偲傟傞恖偼偄傞偺偩傠偆偐偲偁傜偨傔偰巚偭偨乮崱偼娭惣戝妛偺怉搰愭惗偖傜偄偟偐巚偄偮偐側偄丅柤墇巵傕傑偨堘偭偨僕儍儞儖偱榖偑暦偒弌偣傛偆偑丄巹偵偼壸偑廳偄乯丅
懳嵗偟偰偄偰乽巹帺恎偺書偊偰偄傞愨朷姶側偳丄偙偺恖偵偔傜傋偨傜儂儞僩壜垽偄偄傕偺偩側乿偲偁傜偨傔偰巚偭偨丅晝孨偱惍懱嫤夛偺憂巒幰丒栰岥惏嵠愭惗傕晄悽弌偺揤嵥偲鎼傢傟偨偑丄偦偺嵥擻偺僕儍儞儖偼堘偆偐傕偟傟側偄偑丄恖娫偲恖娫偺暥壔偲偄偆偙偲傪傒偮傔峫偊偰偒偨偙偲偵偍偄偰丄桾擵愭惗偺愨朷姶偼晝孨傪挻偊偰偄傞傛偆偵巚偭偨丅傕偭偲傕偙傟偼丣帪戙丣偲偄偆偙偲傕偁傞偲巚偆丅愭戙偺惏嵠愭惗偑朣偔側偭偰傗偑偰巐敿悽婭丅偁偺崰偼傑偩恖娫偺壢妛暥柧偺恑揥偵尰戙傎偳偺堿偼側偐偭偨偐傜丅
崱夞偼偠傔偰巹偼桾擵愭惗偑壒妝尋媶偵偟偐傕拪徾揑側懄嫽偵壗屘怺偔懪偪崬傑傟偰偄傞偺偐丄偍傏傠偘側偑傜傢偐偭偨婥偑偟偨丅
桾擵愭惗偼嶌嬋偝傟偨傕偺傪丄偨偩墘憈偡傞側傜僋儘乕儞偲摨偠偩偲巚傢傟偰偄傞傜偟偄丅乽惗柦傪岅傟傞偺偼懄嫽偟偐側偄乿偦偟偰乽懄嫽偵拋彉偼側傝偨偪摼傞偺偐乿偲偄偆偙偲偑桾擵愭惗偺捛媮偝傟偰偄傞戝偒側僥乕儅偺傛偆偩丅
偝傜偵屆揟偲偼乽夁偓嫀偭偨帪戙傪怱偺掙偐傜惿偟傔傞偐偳偆偐偩乿偲傕岅傜傟丄乽偦傟偼弮悎側姶妎偺捛媮偱傕偁傞乿偲晅偗壛偊傜傟偨丅
偦偺懠偵傕偲偰傕彂偒偒傟側偄偟丄偍傏偊偒傟側偄姶柫傪庴偗偨尵梩偺悢乆偵丄巹側偳偱偼偲偰傕暦偒庤偑偮偲傑傜側偄偺偱丄惀旕娭惣戝妛偺怉搰孾巌愭惗偲懳択偟偰妶帤偵偟偰偄偨偩偗傞傛偆偍婅偄偟偨偑丄尵壓偵乽忕択偱偟傚偆乿偲徫傢傟偨屻偱丄乽偄傗偍榖偟偡傞偩偗側傜杔傕偍夛偄偟偨偄偺偱丄崱搙傑偨婡夛傪傒偮偗偰偍夛偄偟傑偟傚偆乿偲栺懇偟偰壓偝偭偨丅
廔傝偵乽偁偁丄峛栰偝傫偲榖偟偰偨傜傛偗偄愨朷偟偪傖偄傑偟偨傛乿偲嬯徫偝傟偰偟傑偭偨偑丄偙傟偼傑偁懡彮偼榖偑捠偠偰帺暘偺巚偄傪嵞妋擣偟偰偦偆側偭偨偲偄偆偙偲側偺偩傠偆偲偦偺帪偼巚偭偨偑丄婣傝摴丄僸儑僢偲偟偨傜丄榖偑怺偄偲偙傠偱捠偠偢堦憌庘泴姶傪偍傏偊傜傟偨偐傕偟傟側偄偲巚偄丄抪偟偝偵愒柺偟偐偗偨丅
偟偐偟丄摨帪偵愨朷姶偺棟夝偺怺愺偱偙偺傛偆偵姶忣偑摦偔偺偩偐傜丄巹偺愨朷側偳傑偩傑偩僠儍僠側傕偺偩偲婏柇側庒偝傪姶偠丄偦偺暘婥偼妝偵側偭偨丅
偟偐偟丄偁偁偄偆恖偑奺戝妛偵侾恖偔傜偄偄偨側傜偽妛栤丄偦偟偰嫵堢偲偄偆傕偺偺嵼傝條傕偢偄傇傫曄傢傞偐傕偟傟側偄丅傕偭偲傕丄偁偦偙傑偱峴偭偰偟傑偆偲丄廃埻偐傜傕杦偳棟夝偝傟偢懚嵼偟偰偄傞偺偐偄側偄偺偐傕傢偐傜側偄偲偄偆偙偲偵側傞偐傕偟傟側偄偐傜丄偙傟偼側傫偲傕傢偐傜側偄丅
偲偵偐偔丄柤墇巵偲栰岥愭惗偺偍堿偱愨朷傪書偊偮偮丄偝傜偵偦偺愨朷偺惓懱偵偮偄偰丄尒嬌傔偰峴偙偆偲偄偆堄梸偵僄儞僕儞偑偐偐偭偨偙偲偩偗偼妋偐側傛偆偱丄偲傝偁偊偢愭傊恑傔偦偆偱偁傞丅
愨朷偟偰偄傞帪偼愨朷偺乽寎庰乿偑棙偔傜偟偄丅
嶐栭丄媣偟傇傝偵戝嶃偺惛恄壢堛 柤墇峃暥巵偲揹榖偱榖偟丄崱擔偼傗偼傝媣偟傇傝偵丄幮抍朄恖惍懱嫤夛丒恎懱嫵堢尋媶強偺栰岥桾擵愭惗偵偍夛偄偟偰丄偮偔偯偔偲朻摢偺尵梩偑嫻拞偵晜偐傃忋偑偭偰偒偨丅
柤墇巵偵偮偄偰偼丄偙偺儂乕儉儁乕僕偲儕儞僋偟偰偄傞亀柤墇僨傿傾儘乕僌亁偺亀擔婰偺傛偆側恖惗亁傪撉傫偱偄偨偩偗傟偽傢偐傞偲巚偆偑丄僶儕搰偱惛恄揑戝寖恔偵尒晳傟偨傛偆偱丄偦偺捈屻偺俉寧侾侽擔丄僶儕搰偐傜巹偵揹榖偑偁偭偨偑丄偦偺屻偢偭偲梋恔偑懕偄偰偄偨傜偟偔丄嶐擔傑偱楢棈偑側偐偭偨偺偱偁傞丅傕偭偲傕巹偺曽傕偢偭偲愨朷偺掙偵偄偨偐傜丄偁偊偰偙偪傜偐傜傕揹榖傪偟側偐偭偨丅
傕偪傠傫婥偵偼偐偐偭偰偄偨偑丄埲慜傕壗搙偐惛恄忬懺偑晄巚媍偲儕儞僋偟偰偄偨偐傜丄側傫偲側偔柤墇巵傕恏偄忬嫷偩傠偆偲偼巚偭偰偄偨丅偦偟偰埬偺掕丄嶐擔偺揹榖偺條巕偱偼丄乽扤偲傕嫟桳偟偨偄偲巚傢側偄偟偐傕懢屆偺愄偐傜偢偭偲偦偙偵偁偭偨傛偆側愨朷姶乿偵曪傑傟丄姶忣偺晜偒捑傒偺拞偱丄帺傜偺惛恄傪嵹偣偨彫慏傪偳偆偟傛偆傕側偔偝傑傛偭偰偄偨傜偟偄丅偟偐偟丄峫偊偰傒傟偽偙傟傎偳懡偔偺帠審偑婲偒丄壙抣娤偑崿撟偲偟偰偒偰偄傞側偐偱丄偟偐傕偦傟傜偵嵟傕東楳偝傟偰偄傞恖払偺榖傪暦偔偲偄偆怑嬈偱丄恖娫側傜傆傝傑傢偝傟側偄敜偑側偄乮帺暘偺姶妎傪撦傜偣丄宍偳偍傝偺幙栤傪偟偰丄偨偩婡夿揑偵栻傪弌偡偩偗偺惛恄壢堛側傜塭嬁傪庴偗傞偙偲傕側偄偐傕偟傟側偄偑乯丅
徻偟偄榖偼傑偩暦偄偰側偄偑乮傕偭偲傕偦傟偑偆傑偔尵梩偵側傞偐偳偆偐傕傢偐傜側偄偑乯丄柤墇巵偺係侽擭嬤偔偺恖惗偺側偐偱旕忢偵戝偒側愡栚傪寎偊偰偄傞傛偆偩丅
偦偟偰崱擔丄惍懱嫤夛偱栰岥桾擵愭惗偲俆儢寧傇傝偵偍夛偄偡傞丅
偄傑傑偱悢廫夞偍夛偄偟偰丄忢偵偦偺巚嶕偺怺偝偲姶惈偺塻偝偵僞儊懅傪偮偐偣懕偗傜傟偰偒偨偑丄崱夞傕儂僩儂僩姶扱丅
偙傟傎偳偺揤嵥偵側傞偲丄偄偭偨偄廫暘偵榖偺庴偗傪偲傟傞恖偼偄傞偺偩傠偆偐偲偁傜偨傔偰巚偭偨乮崱偼娭惣戝妛偺怉搰愭惗偖傜偄偟偐巚偄偮偐側偄丅柤墇巵傕傑偨堘偭偨僕儍儞儖偱榖偑暦偒弌偣傛偆偑丄巹偵偼壸偑廳偄乯丅
懳嵗偟偰偄偰乽巹帺恎偺書偊偰偄傞愨朷姶側偳丄偙偺恖偵偔傜傋偨傜儂儞僩壜垽偄偄傕偺偩側乿偲偁傜偨傔偰巚偭偨丅晝孨偱惍懱嫤夛偺憂巒幰丒栰岥惏嵠愭惗傕晄悽弌偺揤嵥偲鎼傢傟偨偑丄偦偺嵥擻偺僕儍儞儖偼堘偆偐傕偟傟側偄偑丄恖娫偲恖娫偺暥壔偲偄偆偙偲傪傒偮傔峫偊偰偒偨偙偲偵偍偄偰丄桾擵愭惗偺愨朷姶偼晝孨傪挻偊偰偄傞傛偆偵巚偭偨丅傕偭偲傕偙傟偼丣帪戙丣偲偄偆偙偲傕偁傞偲巚偆丅愭戙偺惏嵠愭惗偑朣偔側偭偰傗偑偰巐敿悽婭丅偁偺崰偼傑偩恖娫偺壢妛暥柧偺恑揥偵尰戙傎偳偺堿偼側偐偭偨偐傜丅
崱夞偼偠傔偰巹偼桾擵愭惗偑壒妝尋媶偵偟偐傕拪徾揑側懄嫽偵壗屘怺偔懪偪崬傑傟偰偄傞偺偐丄偍傏傠偘側偑傜傢偐偭偨婥偑偟偨丅
桾擵愭惗偼嶌嬋偝傟偨傕偺傪丄偨偩墘憈偡傞側傜僋儘乕儞偲摨偠偩偲巚傢傟偰偄傞傜偟偄丅乽惗柦傪岅傟傞偺偼懄嫽偟偐側偄乿偦偟偰乽懄嫽偵拋彉偼側傝偨偪摼傞偺偐乿偲偄偆偙偲偑桾擵愭惗偺捛媮偝傟偰偄傞戝偒側僥乕儅偺傛偆偩丅
偝傜偵屆揟偲偼乽夁偓嫀偭偨帪戙傪怱偺掙偐傜惿偟傔傞偐偳偆偐偩乿偲傕岅傜傟丄乽偦傟偼弮悎側姶妎偺捛媮偱傕偁傞乿偲晅偗壛偊傜傟偨丅
偦偺懠偵傕偲偰傕彂偒偒傟側偄偟丄偍傏偊偒傟側偄姶柫傪庴偗偨尵梩偺悢乆偵丄巹側偳偱偼偲偰傕暦偒庤偑偮偲傑傜側偄偺偱丄惀旕娭惣戝妛偺怉搰孾巌愭惗偲懳択偟偰妶帤偵偟偰偄偨偩偗傞傛偆偍婅偄偟偨偑丄尵壓偵乽忕択偱偟傚偆乿偲徫傢傟偨屻偱丄乽偄傗偍榖偟偡傞偩偗側傜杔傕偍夛偄偟偨偄偺偱丄崱搙傑偨婡夛傪傒偮偗偰偍夛偄偟傑偟傚偆乿偲栺懇偟偰壓偝偭偨丅
廔傝偵乽偁偁丄峛栰偝傫偲榖偟偰偨傜傛偗偄愨朷偟偪傖偄傑偟偨傛乿偲嬯徫偝傟偰偟傑偭偨偑丄偙傟偼傑偁懡彮偼榖偑捠偠偰帺暘偺巚偄傪嵞妋擣偟偰偦偆側偭偨偲偄偆偙偲側偺偩傠偆偲偦偺帪偼巚偭偨偑丄婣傝摴丄僸儑僢偲偟偨傜丄榖偑怺偄偲偙傠偱捠偠偢堦憌庘泴姶傪偍傏偊傜傟偨偐傕偟傟側偄偲巚偄丄抪偟偝偵愒柺偟偐偗偨丅
偟偐偟丄摨帪偵愨朷姶偺棟夝偺怺愺偱偙偺傛偆偵姶忣偑摦偔偺偩偐傜丄巹偺愨朷側偳傑偩傑偩僠儍僠側傕偺偩偲婏柇側庒偝傪姶偠丄偦偺暘婥偼妝偵側偭偨丅
偟偐偟丄偁偁偄偆恖偑奺戝妛偵侾恖偔傜偄偄偨側傜偽妛栤丄偦偟偰嫵堢偲偄偆傕偺偺嵼傝條傕偢偄傇傫曄傢傞偐傕偟傟側偄丅傕偭偲傕丄偁偦偙傑偱峴偭偰偟傑偆偲丄廃埻偐傜傕杦偳棟夝偝傟偢懚嵼偟偰偄傞偺偐偄側偄偺偐傕傢偐傜側偄偲偄偆偙偲偵側傞偐傕偟傟側偄偐傜丄偙傟偼側傫偲傕傢偐傜側偄丅
偲偵偐偔丄柤墇巵偲栰岥愭惗偺偍堿偱愨朷傪書偊偮偮丄偝傜偵偦偺愨朷偺惓懱偵偮偄偰丄尒嬌傔偰峴偙偆偲偄偆堄梸偵僄儞僕儞偑偐偐偭偨偙偲偩偗偼妋偐側傛偆偱丄偲傝偁偊偢愭傊恑傔偦偆偱偁傞丅
埲忋侾擔暘乛宖嵹擔 暯惉侾俀擭俉寧俀係擔(栘乯
俀侽侽侽擭俉寧俀俁擔乮悈乯
愨朷傪書偊丄偦偺惓懱傪尒撏偗傛偆偲巚偆偲丄傑偨偦傟側傝偺朲偟偝偑墴偟婑偣偰偔傞丅
崱擔偼嬎朁崅峑偺嬥揷怢晇愭惗偐傜揹榖偑偁傝丄嬥揷愭惗偑僶僗働僢僩儃乕儖偺嶨帍亀僗億乕僣丒僀儀儞僩 僶僗働僢僩儃乕儖亁乮僗億乕僣C儀儞僩幮乯俉寧崋偺庢嵽傪庴偗偨婰帠偺撪梕傪俥俙倃偱憲偭偰壓偝偭偨丅壗傗傜巹偺柤慜偑揰乆偲弌偰偔傞偑丄偙偲丄偙偺嬎朁崅峑偺僶僗働僢僩儃乕儖晹偵娭偟偰偼丄尓懟偱傕壗偱傕側偔巹偼扨偵僸儞僩傪嵎偟忋偘偨偵夁偓側偄丅偮傑傝丄僙儞僗偑傛偔巙偺偁傞曽偼丄傎傫偺嬐偐側僸儞僩偐傜傕戝偒側惉壥傪捦傒弌偡偲偄偆尒杮偺傛偆側榖側偺偱偁傞丅
崱擔偼傑偨丄亀俽俿倀俢俬俷 倁俷俬俠俤亁侾侽寧崋乮俋寧忋弡敪攧梊掕乯偺嵟廔峑惓傪揹榖偱偟偨丅偙偺僀儞僞價儏乕偼偐側傝偺帤悢偑偁傝丄巹偑嵟嬤巚偭偰偄傞偙偲丄姶偠偨偙偲傪偐側傝尵傢偣偰傕傜偊偨丅
偙偺応傪庁傝偰僀儞僞價儏傾乕偺忋栰孿堦巵偲曇廤幰偺怺戲宑懢巵偵姶幱偺堄傪昞偟偨偄丅
偦偆偄偊偽崱寧俁侾擔偺栘梛擔偼丄戝嶃偺挬擔僇儖僠儍乕僙儞僞乕偱丄惛恄壢堛偺柤墇峃暥巵偺懳榖儈儏乕僕傾儉偺俀夞栚偑奐偐傟傞丅崱夞偺柤墇巵偺屼憡庤偼丄偐偺娭惣戝妛嫵庼丒怉搰孾巌愭惗丅巹傕峴偒偨偄偺偩偑梊掕偑媗傑偭偰偄偰峴偗側偄丅
傑偩惾偵懡彮梋桾偑偁傞傛偆側偺偱屼娭怱偺偁傞曽偼惀旕峴偐傟傞偙偲傪偍姪傔偟偨偄丅
栤崌偣偼挬擔僇儖僠儍乕僙儞僞乕丒戝嶃傑偱乮拞擵搰丒挬擔怴暦價儖撪丒噭侽俇亅俇俀俀俀亅俆俀俀俀丒梫梊栺乯丅
愨朷傪書偊丄偦偺惓懱傪尒撏偗傛偆偲巚偆偲丄傑偨偦傟側傝偺朲偟偝偑墴偟婑偣偰偔傞丅
崱擔偼嬎朁崅峑偺嬥揷怢晇愭惗偐傜揹榖偑偁傝丄嬥揷愭惗偑僶僗働僢僩儃乕儖偺嶨帍亀僗億乕僣丒僀儀儞僩 僶僗働僢僩儃乕儖亁乮僗億乕僣C儀儞僩幮乯俉寧崋偺庢嵽傪庴偗偨婰帠偺撪梕傪俥俙倃偱憲偭偰壓偝偭偨丅壗傗傜巹偺柤慜偑揰乆偲弌偰偔傞偑丄偙偲丄偙偺嬎朁崅峑偺僶僗働僢僩儃乕儖晹偵娭偟偰偼丄尓懟偱傕壗偱傕側偔巹偼扨偵僸儞僩傪嵎偟忋偘偨偵夁偓側偄丅偮傑傝丄僙儞僗偑傛偔巙偺偁傞曽偼丄傎傫偺嬐偐側僸儞僩偐傜傕戝偒側惉壥傪捦傒弌偡偲偄偆尒杮偺傛偆側榖側偺偱偁傞丅
崱擔偼傑偨丄亀俽俿倀俢俬俷 倁俷俬俠俤亁侾侽寧崋乮俋寧忋弡敪攧梊掕乯偺嵟廔峑惓傪揹榖偱偟偨丅偙偺僀儞僞價儏乕偼偐側傝偺帤悢偑偁傝丄巹偑嵟嬤巚偭偰偄傞偙偲丄姶偠偨偙偲傪偐側傝尵傢偣偰傕傜偊偨丅
偙偺応傪庁傝偰僀儞僞價儏傾乕偺忋栰孿堦巵偲曇廤幰偺怺戲宑懢巵偵姶幱偺堄傪昞偟偨偄丅
偦偆偄偊偽崱寧俁侾擔偺栘梛擔偼丄戝嶃偺挬擔僇儖僠儍乕僙儞僞乕偱丄惛恄壢堛偺柤墇峃暥巵偺懳榖儈儏乕僕傾儉偺俀夞栚偑奐偐傟傞丅崱夞偺柤墇巵偺屼憡庤偼丄偐偺娭惣戝妛嫵庼丒怉搰孾巌愭惗丅巹傕峴偒偨偄偺偩偑梊掕偑媗傑偭偰偄偰峴偗側偄丅
傑偩惾偵懡彮梋桾偑偁傞傛偆側偺偱屼娭怱偺偁傞曽偼惀旕峴偐傟傞偙偲傪偍姪傔偟偨偄丅
栤崌偣偼挬擔僇儖僠儍乕僙儞僞乕丒戝嶃傑偱乮拞擵搰丒挬擔怴暦價儖撪丒噭侽俇亅俇俀俀俀亅俆俀俀俀丒梫梊栺乯丅
埲忋侾擔暘乛宖嵹擔 暯惉侾俀擭俉寧俀俇擔(搚乯
俀侽侽侽擭俉寧俀俇擔乮搚乯
愮梩巗偺晲摴娰偱庤棤寱弍傪堦斒偵嫵偊傜傟偰偄傞偲偄偆敧妏棳庤棤寱弍偺憂巒幰丒敿揷埲堦巘斖偐傜偍揹榖傪偄偨偩偄偨偺偼丄偨偟偐崱寧侾俈擔偩偭偨偲巚偆丅
偍揹榖偱偼丄棃擭丄崄庢恄媨偱慡崙偺捈懪朄偺庤棤寱弍偺揱彸幰丄弍幰傪廤傔偨墘晲夛傪嵜偟偨偄偺偱丄偦偺愜偍彽偒偟偨偄丄偲偺偍榖偩偭偨丅
敧妏棳偲敿揷巘斖偵偮偄偰偼晲弍帍偱偦偺屼柤慜傪嵟嬤抦傝丄岞棫偺晲摴娰偱庤棤寱弍傪嫵偊傜傟偰偄傞偲偼捒偟偄丄偲巚偭偰偄偨偺偱丄棃擭偺墘晲夛偵弌応偡傞丄偟側偄偼偲傕偐偔丄偳偆偄偆偄偒偝偮偱晲摴娰偱庤棤寱弍傪峀偔堦斒偵嫵偊偰偍傜傟傞偺偐丄偦偺偙偲傪惀旕偆偐偑偄偨偄偟丄敧妏棳偲偄偆庤棤寱弍傕攓尒偟偨偄偲巚偭偨偺偱丄弌棃傟偽嬤乆堦搙屼宮屆傪攓尒偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲偍婅偄偟偨偲偙傠丄乽惀旕偳偆偧丄偙偪傜偙偦攓尒偟偨偄乿偲偍偭偟傖偰偄偨偩偒丄偍彽偒傪庴偗偨妴岲偵側偭偰偟傑偭偨丅
偦偺屻丄嬶懱揑側擔帪偺懪崌偣傪偟偨偲偙傠丄懡偔偺栧掜偺曽乆傕棃傜傟傞偲偺偙偲丅懠棳偺摴応偵巉偭偰丄扨側傞墘晲偩偗偱偼側偔丄幙栤傪偄偨偩偄偨傜丄嬶懱揑愢柧傕偡傞偙偲偵側傞偩傠偆偟乧偲鏢鏞偡傞巚偄傕偁偭偨偑丄敧妏棳偼怴偟偔憂棳偝傟偨庤棤寱弍偱丄偁傞摿掕偺揱摑傪庴偗宲偄偱偄傞傢偗偱偼側偄偲偺偙偲丅偟偐傕惀旕攓尒偟偨偄偲廳偹偰偍偭偟傖偭偰偄偨偩偄偨偺偱丄巹傕尰嵼巹偺抦傝摼傞尷傝偺偙偲偼偍榖偟丄媄傕偍尒偣偟傛偆偲怱偵嬫愗傝傪偮偗偰丄崱擔巉偭偨偺偱偁傞丅
摓拝偟偰偡偖丄傑偢壗傛傝傕敿揷愭惗偵丄側偤巗偺晲摴娰偱庤棤寱弍傪岞奐偟偰嫵偊傞偙偲偑弌棃傞偺偐偆偐偑偄偨偄偲巚偭偨偑丄偦偺偙偲偼偍夛偄偟偰偛垾嶢偟偨帪偵偡偖柧傜偐偲側偭偨丅側傫偲敿揷愭惗偼丄偙偺愮梩巗晲摴娰偺娰挿傪柋傔傜傟偰偄偨偺偱偁傞丅
拝懼偊偰偡偖宮屆応偱偁傞媩摴応偵巉偆丅偡傞偲懡彮偼梊憐偟偰偄偨偑丄側傫偲係侽恖傎偳偺敧妏棳傪宮屆偝傟偰偄傞曽乆偑僘儔儕偲嵗偭偰巹傪懸偭偰偄偰壓偝偭偨偺偱偁傞丅
敿揷愭惗偐傜屼徯夘偄偨偩偒丄懀偝傟傞傑傑偵巹偺懪寱朄偺奣梫傪偍榖偟偟丄梡堄偝傟偰偄偨忯偵寱傪懪偭偨丅庤偑娋偱擲傞壞丄幍娫埲忋傪懪偮偺偼嫀擭傑偱偩偭偨傜柌暔岅偩偭偨偑丄傑偁壗偲偐捠偡偙偲偑偱偒偨丅
偨偩丄栭娫偺媩摴応偲偄偆偙偲傕偁偭偰徠柧偑埫偐偭偨偣偄偐丄偳偆傕娫崌偄偺撉傒偑偄傑傂偲偮偟偭偔傝棃側偐偭偨偑丄偦傟偼巹偺枹弉偺偣偄偱偁傠偆丅
偦偺屻丄搧偵傛傞忯昞傪姫偄偨傕偺偺帋巃傕梫朷偝傟丄巹傕壗擭傇傝偐偵巃偭偰傒偨偑丄偙偺曽偼傑偭偨偔怱偵偐側傢側偐偭偨丅傂偲偮偵偼嵟嬤懪寱偱懱偺傾僜價傪偲偭偰寱傪懪偮偙偲偐傜丄寱弍偺巃媄偵偍偄偰傕丄懱偺傾僜價傪偲傞懱偺巊偄曽傪岺晇拞偱孶嵕巃傝偑戝偒偔曄傢傝偼偠傔偰偄傞帪偱偁傞偨傔丄幚嵺偵暔傪巃傞偲側偭偨帪丄恎懱偑偳偭偪偮偐偢偱柪偭偰偟傑偭偨偺偩偲巚偆丅
偦偺懠偼懡彮敳搧弍傗寱弍丄忨弍側偳傕峴側偭偨偑丄壗傛傝報徾揑偩偭偨偺偼庤棤寱偵娭偟偰丄偦偺懪朄偵偍偗傞懱偺巊偄曽偼傕偪傠傫丄巹偑梡偄偰偄傞寱偺峾嵽偺庬椶摍偺屼幙栤傑偱庴偗偨偙偲偱偁傞丅偳偆峫偊偰傒偰傕懡偔偺恖偺慜偱庤棤寱弍傪墘晲偟偰丄巹帺恎崱夞傎偳徻偟偄夝愢傪偟偨偙偲側偳堦搙傕側偐偭偨丅
敿揷愭惗偼壗搙傕乽偄傗丄抦傜側偄恖偼巋偭偰偁偨傝慜偩偲巚偭偰偙偺擄偟偝側傫偰傢偐傜側偄傫偱偡偗偳丄偙偙偵棃偰偄傞恖払偼丄偦偺擄偟偝偑廫暘傢偐偭偰偄傑偡偐傜乿偲岥偵偝傟偰偄偨偑丄偦偆偟偨嫟摨棟夝偺婎斦偑偁偭偨偨傔偵巹傕帺慠偲擬偑擖偭偨偺偩傠偆丅
敿揷埲堦愭惗傪偼偠傔堦栧偺曽乆偵丄偙偺応傪庁傝偰屼楃傪怽偟忋偘偨偄丅
愮梩巗偺晲摴娰偱庤棤寱弍傪堦斒偵嫵偊傜傟偰偄傞偲偄偆敧妏棳庤棤寱弍偺憂巒幰丒敿揷埲堦巘斖偐傜偍揹榖傪偄偨偩偄偨偺偼丄偨偟偐崱寧侾俈擔偩偭偨偲巚偆丅
偍揹榖偱偼丄棃擭丄崄庢恄媨偱慡崙偺捈懪朄偺庤棤寱弍偺揱彸幰丄弍幰傪廤傔偨墘晲夛傪嵜偟偨偄偺偱丄偦偺愜偍彽偒偟偨偄丄偲偺偍榖偩偭偨丅
敧妏棳偲敿揷巘斖偵偮偄偰偼晲弍帍偱偦偺屼柤慜傪嵟嬤抦傝丄岞棫偺晲摴娰偱庤棤寱弍傪嫵偊傜傟偰偄傞偲偼捒偟偄丄偲巚偭偰偄偨偺偱丄棃擭偺墘晲夛偵弌応偡傞丄偟側偄偼偲傕偐偔丄偳偆偄偆偄偒偝偮偱晲摴娰偱庤棤寱弍傪峀偔堦斒偵嫵偊偰偍傜傟傞偺偐丄偦偺偙偲傪惀旕偆偐偑偄偨偄偟丄敧妏棳偲偄偆庤棤寱弍傕攓尒偟偨偄偲巚偭偨偺偱丄弌棃傟偽嬤乆堦搙屼宮屆傪攓尒偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲偍婅偄偟偨偲偙傠丄乽惀旕偳偆偧丄偙偪傜偙偦攓尒偟偨偄乿偲偍偭偟傖偰偄偨偩偒丄偍彽偒傪庴偗偨妴岲偵側偭偰偟傑偭偨丅
偦偺屻丄嬶懱揑側擔帪偺懪崌偣傪偟偨偲偙傠丄懡偔偺栧掜偺曽乆傕棃傜傟傞偲偺偙偲丅懠棳偺摴応偵巉偭偰丄扨側傞墘晲偩偗偱偼側偔丄幙栤傪偄偨偩偄偨傜丄嬶懱揑愢柧傕偡傞偙偲偵側傞偩傠偆偟乧偲鏢鏞偡傞巚偄傕偁偭偨偑丄敧妏棳偼怴偟偔憂棳偝傟偨庤棤寱弍偱丄偁傞摿掕偺揱摑傪庴偗宲偄偱偄傞傢偗偱偼側偄偲偺偙偲丅偟偐傕惀旕攓尒偟偨偄偲廳偹偰偍偭偟傖偭偰偄偨偩偄偨偺偱丄巹傕尰嵼巹偺抦傝摼傞尷傝偺偙偲偼偍榖偟丄媄傕偍尒偣偟傛偆偲怱偵嬫愗傝傪偮偗偰丄崱擔巉偭偨偺偱偁傞丅
摓拝偟偰偡偖丄傑偢壗傛傝傕敿揷愭惗偵丄側偤巗偺晲摴娰偱庤棤寱弍傪岞奐偟偰嫵偊傞偙偲偑弌棃傞偺偐偆偐偑偄偨偄偲巚偭偨偑丄偦偺偙偲偼偍夛偄偟偰偛垾嶢偟偨帪偵偡偖柧傜偐偲側偭偨丅側傫偲敿揷愭惗偼丄偙偺愮梩巗晲摴娰偺娰挿傪柋傔傜傟偰偄偨偺偱偁傞丅
拝懼偊偰偡偖宮屆応偱偁傞媩摴応偵巉偆丅偡傞偲懡彮偼梊憐偟偰偄偨偑丄側傫偲係侽恖傎偳偺敧妏棳傪宮屆偝傟偰偄傞曽乆偑僘儔儕偲嵗偭偰巹傪懸偭偰偄偰壓偝偭偨偺偱偁傞丅
敿揷愭惗偐傜屼徯夘偄偨偩偒丄懀偝傟傞傑傑偵巹偺懪寱朄偺奣梫傪偍榖偟偟丄梡堄偝傟偰偄偨忯偵寱傪懪偭偨丅庤偑娋偱擲傞壞丄幍娫埲忋傪懪偮偺偼嫀擭傑偱偩偭偨傜柌暔岅偩偭偨偑丄傑偁壗偲偐捠偡偙偲偑偱偒偨丅
偨偩丄栭娫偺媩摴応偲偄偆偙偲傕偁偭偰徠柧偑埫偐偭偨偣偄偐丄偳偆傕娫崌偄偺撉傒偑偄傑傂偲偮偟偭偔傝棃側偐偭偨偑丄偦傟偼巹偺枹弉偺偣偄偱偁傠偆丅
偦偺屻丄搧偵傛傞忯昞傪姫偄偨傕偺偺帋巃傕梫朷偝傟丄巹傕壗擭傇傝偐偵巃偭偰傒偨偑丄偙偺曽偼傑偭偨偔怱偵偐側傢側偐偭偨丅傂偲偮偵偼嵟嬤懪寱偱懱偺傾僜價傪偲偭偰寱傪懪偮偙偲偐傜丄寱弍偺巃媄偵偍偄偰傕丄懱偺傾僜價傪偲傞懱偺巊偄曽傪岺晇拞偱孶嵕巃傝偑戝偒偔曄傢傝偼偠傔偰偄傞帪偱偁傞偨傔丄幚嵺偵暔傪巃傞偲側偭偨帪丄恎懱偑偳偭偪偮偐偢偱柪偭偰偟傑偭偨偺偩偲巚偆丅
偦偺懠偼懡彮敳搧弍傗寱弍丄忨弍側偳傕峴側偭偨偑丄壗傛傝報徾揑偩偭偨偺偼庤棤寱偵娭偟偰丄偦偺懪朄偵偍偗傞懱偺巊偄曽偼傕偪傠傫丄巹偑梡偄偰偄傞寱偺峾嵽偺庬椶摍偺屼幙栤傑偱庴偗偨偙偲偱偁傞丅偳偆峫偊偰傒偰傕懡偔偺恖偺慜偱庤棤寱弍傪墘晲偟偰丄巹帺恎崱夞傎偳徻偟偄夝愢傪偟偨偙偲側偳堦搙傕側偐偭偨丅
敿揷愭惗偼壗搙傕乽偄傗丄抦傜側偄恖偼巋偭偰偁偨傝慜偩偲巚偭偰偙偺擄偟偝側傫偰傢偐傜側偄傫偱偡偗偳丄偙偙偵棃偰偄傞恖払偼丄偦偺擄偟偝偑廫暘傢偐偭偰偄傑偡偐傜乿偲岥偵偝傟偰偄偨偑丄偦偆偟偨嫟摨棟夝偺婎斦偑偁偭偨偨傔偵巹傕帺慠偲擬偑擖偭偨偺偩傠偆丅
敿揷埲堦愭惗傪偼偠傔堦栧偺曽乆偵丄偙偺応傪庁傝偰屼楃傪怽偟忋偘偨偄丅
埲忋侾擔暘乛宖嵹擔 暯惉侾俀擭俉寧俀俋擔(壩乯