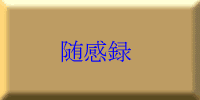 |
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2001年 2005年 2009年 2013年 2002年 2006年 2010年 2014年 2003年 2007年 2011年 2016年 2004年 2008年 2012年 |
"寸暇ない"という表現は、現在の私にとって大袈裟ではなく、実状そのものとなってきた。この随感録も30日から書きたい、書きたいと思いながら、4日も経ってしまった。
この間、最優先事項は井上雄彦氏との本のゲラの赤入れであった筈だが、30日は山のような問い合わせへの対応と夕方から音楽家の人達への初めての講座、その打ち上げで殆ど進まなかった。
31日は一番時間をあてられる筈だったが、久しぶりの桑田氏の来館の後も、やむにやまれぬ事情でなんと終日稽古。尤も稽古をすれば気づきがあるから、始めれば私もノッてしまう。
太刀奪りの体捌きに、25日バスケットボールの選手の質問に応えて思いついた形を逆に転用すると有効なことに気づく。この他、平蜘蛛返しの立ち技への応用的なもの、太刀奪りの足捌きで出ると間の詰め方が速やかなこと、体術での突きの起こりをとらえて叩き落としやすいことなどの気づきがあった。
翌日もまた来客。この日こそは何とがゲラをと思いつつ、私にとっても重要な用件があって夕方までゲラの赤入れは出来なかった。それでも夕方から夜にかけて100ページ近くは何とかやったが、体調が思わしくなく、臍を炊きたてご飯で温めるという野口先生から指示された方法を試み、5時間ほど深く眠って今朝から赤入れ。但し今日は赤坂で夕方から新技術研究会があったため、出来るだけやってゲラを持ってあたふたと家を出る。
新技術研究会へは、かつてホンダのアシモ開発に関わり、いま金沢工業大学で客員教授を務められている田上勝俊先生から、講師の要請を受けて出向いたもの。
様々な企業の中堅技術者の方々10名ほどを前に動きと解説を行なう。大変興味をもって聴いて頂けたので話し甲斐があった。その後の打ち上げでも話に花が咲きかけたが、7時過ぎ対談本のゲラのことがあるので、話が蕾のうちに失礼して市谷田町のアークへ。ここで赤入れの続きを一気にやり、何とか終電の1つ前に乗って帰宅。それにしても歩きながらや乗り物の窓越しだけの花見は今年だけにしたい。
ここ2,3日、私の家のFAXが入らなくなっていたようで、今日の午前中は殆どその対応で終わる。はじめは又電話機の故障かと思ったが、どうやらADSLを入れた為らしい。それで、いろいろやって何とか入るようになったが、まだ不安定。忙しい中、このような突発事態が起こると本当に疲れる。
とにかく連日次々と場面が変わったことが起こるので、数日前のことが数週間前に感じる。しかし記録を見返してから記憶を辿ると、4日の日曜日、田端のT道場で、野間道場でも知られているというM先生と会談している。これはT氏の仲介で『剣道日本』誌の取材も兼ねてのものであった。この日、つくづく「時代も変わったものだ」と実感する。その後は千代田での会。
そして5日は山ノ上ホテルで午後1時から4人がかりで9時間以上かけて宝島社の本の企画のテープ録り。内容が重かったせいもあり、土曜日からの寝不足で終わった時は腰が立たないほど疲れた。ただホテルの部屋が私が今まで泊まった事もないような豪華な広い部屋だったので、翌日の10時頃までゆっくりと休めた。
6日は山ノ上ホテルからアークに寄って、新潮社の新潮クラブへ。ここで去年、雑誌『ウォーキング』で対談させて頂いた森下はるみ先生と2度目の対談。ダンサーの山田うん女史、ライターの田中聡氏、編集者の足立女史と、よく気心の知れた方々が同席して下さったので、ここでの4時間は、たちまち過ぎた感じだった。
しかし、その後は又慌しく約1キロ離れた旅館"和可菜"へ。ここは先月17日浅野忠信氏と会ったところだが、今回はNHK大阪のテレビからの依頼での撮り。内容は、土方歳三に関する質問に答えるものだったが、私の動きも撮っておきたいとの事で抜刀を何本か抜く。ただこの時、急にカメラが寄ってきたので、円月抜をつまって抜いてしまい、鞘の鯉口を破損させるという未だかつてした事のないミスを犯してしまった。ただ、刀身も無事で、誰も怪我をしなかった事は幸いだった。というか、この事故の一番の収穫は、鯉口を壊しながら「しまった!」とか、「ああ、こんなふうにやるんじゃなかった」という後悔の念が0,5秒も浮かばなかったこと。
「"運命の定・不定"の体感的把握」という私の生涯のテーマは、21歳の時から殆ど進んでいないと思っていたが、7年前、刀の切先をやはり円月抜の失敗で飛ばした時よりも、更に気持ちの動揺が少なかったから、「ああ、こんな自分でも多少は進んでいるのだ」と思えて、これには小さな満足感があった。
それにしても、とにかく武術は「居つかぬこと」「準備をしないこと」がどれほど重要であるかを、より深く認識させられた。
体調は、もう1日の内でも山あり谷ありで、「お体はどうですか?」と尋ねられても何とも答えようがない。しかし、こんな事をしていると、先日「自然破壊に心を傷められている人が、自分の身体という自然破壊をこれ以上続けていいんですか」と突っ込んでこられた畏友のE氏から又電話をもらうハメになりそうだ。
しかし9日は池袋の講座。その前に新宿で出版社の人と企画の相談。10日は午前中に『文芸春秋』誌の依頼の対談。その後も講座やら収録やらで来週半ばまで埋まり、週末は九州だから、もう本当に実際体調が崩れるまでは止められないかも知れない。
ただ、今はなぜか体調よりも私自身は意欲の低下が気がかり・・。それは体が壊れても意欲がある方が、まだ自分が自分であり続けている気がするからだろう。しかし、意欲は努力や頑張りでどうなるわけでもないから、成り行きに任せるしかないだろう。
昨夜、複数の企画の相談やらインタビューを池袋コミュニティ・カレッジの講座の前後に入れていたため、帰途はガックリ疲れていたが、家近くになって中国滞在中と思っていた岡山の光岡英稔師から電話。てっきり中国からの電話だと思ったが、聞くと北京で意拳の創始者王向斎老師の次女に当たられる王玉芳女史と会い、これからあらためて珠海の韓星橋老師の所へ向かうため、一旦帰国して関空のホテルに居るとの事。そして、それから約1時間、王女史との出会いの様子やら王女史からもたらされたという王向斎老師に関する貴重な情報を聞くことが出来た。
話の様子からも韓星橋老師が王向斎門下で格別な存在であった事が伺え、その韓老師に見込まれ入室弟子となった光岡師の資質と巡り合わせの不思議さにあらためて光岡師が時代を背負う星の許に生まれていることを感じ、何だか感慨に胸が熱くなった。
尤も、この胸の熱さは光岡師が韓氏意拳を正式に学ぶことになった経緯に私が微妙に絡んでいて、その事で律儀にも光岡師が私に恩を感じられているらしい誠実さが伝わってきた事もある。好漢ますます技を磨き、伝説の達人に並ぶほどの技を現代に蘇らせて頂きたいと願っている。何と言っても現在私の知る限り、光岡師がその世界に入る可能性が最も高い人物である。光岡師との電話の後も、どうしても連絡を取らなければならない電話が3件あり、寝たのは3時を回っていた。
そして今日は8時には起きて仕度をし、月刊『文藝春秋』の企画による対談のため、初台にある畑村洋太郎工学院大学教授のオフィスへ。『失敗学』を提唱され、多くの企業人の関心を集めている畑村先生は、私が以前『文藝春秋』誌で述べたものに対して「全く賛成です」と驚くほどの支持を表明して下さり、そのため2時間の予定の対談が30分近くもオーバーしてしまった。
午後は道場に何人もの人が来て、いろいろ動いたり写真撮りやら取材やら。昨日の体調からみて、今日1日体がもつかなあと思ったが、いろいろと体を動かして気づきもあったせいか、何とか夜までもったし、技の面では体幹による斬りの体という気づきがあって、体当たり等に進展があった。そして、更にこの体幹による斬りの体は掌の向きの術理と合わせると、打剣にも今までにない新たな打法(具体的には掌と剣の摩擦の多い時の打ち方)に新生面を開きつつある。
今日は、体調が悪い時はやはり体を動かさねばダメだと痛感した。
「熟々(つらつら)考えるに・・」という言い方は、この頃あまり耳にしないが、3日ほど前からしきりに頭の中に浮かんでくる。
何をつらつら考えたかというと、このどうにもならないほどの忙しさに振り回されている最近の私自身の生活についてである。
この随感録だけは、よほど忙しくても3日に1度くらいは書こうと思っているのだが(間が空くと私の健康状態を大変気遣って下さる方がいらっしゃるので)、それもついこの頃は間が空いてしまう。
部屋も道場も片づかないし、出さねばならぬ手紙、かけねばならない電話も必要量の何分の1にも達しないうちに夜がきて朝が明けてしまう。このままでは一体何がなんだか分からないうちに人生を卒業させられてしまいそうだ。「なりゆきを愛して」と言っていたが、「なりゆきに振り回されて」いては「愛している」ヒマもない。病気ということにして、当分依頼は断ろうかと本気で考えている。
それにしても今週に入ってからは濃い日が続いた。11日の日曜日は、夜、名越氏らと身体教育研究所へ。名越氏がTVの『グータン』へ出ている事もあって、久しぶりに野口裕之先生から体癖論についての息を呑むような具体的かつ掘り下げた話をうかがう。お蔭で帰りは3時近く。それにしても野口先生が私の体を御覧になった時に現れたという兎が何を指してのことなのか、今後の展開が楽しみである。
12日は田町での講座。この日、質問に答えていて、私の上に相手がのしかかってくる寝技的状況で、それを両足の巴投げ的に外してしまう技をその場で思いついた。
翌13日は塩浜のスタジオでTVの収録。これは女優の高木美保さんが司会をつとめられている番組で介護を取り上げたいとの事で制作会社から依頼があり、引き受けたのである。介護に関しては、最近私の方式を取り入れて活躍されている方から「今までの方法で腰に負担がかかっていたのとは比べものにならないくらい楽で感謝してます」とのコメントを頂いていたので、私の発案した方法が広まれば介護に関わる方々にとっても朗報になるだろうし、私のやり方を取り入れ成果を挙げられている方々の今後の活躍を応援することにもなると判断し、TVには極力出ないことにしていたが、今回は引き受けたのである。
この場で、全介護状態の人を椅子から抱き上げるのに、私の技の「抱え上げ」や「平蜘蛛返し」と同じ足裏の垂直離陸を使うと、驚くほど楽に抱き上げられることを発見した。
しかし、とにかく余りにもやることが多すぎて、右を見ても左を見てもやりかけの事ばかり(この随感録も14日に半分書いて、結局今日16日まで引きずってしまった)。どうしても行かねばならない予定はこなさねばならないから、今日は九州へ。17日は自然農の川口由一氏との対談。これは私も楽しみにしていたものだから、この時ぐらいは忙しさを忘れて私の思いを尽くしたいと思う。
26日は、井上雄彦氏との共著、『武(ぶ)』が宝島社から刊行の予定。
今日、旅先から電話で話した方からも、「随感録の間が空くと心配で・・」と、私の健康を案じて下さるお言葉を頂き恐縮すると共に、これからはコマ切れでも「随感録」を書いてゆこうと思っている。
明日は川口氏との対談だが、只でさえ飛行機が苦手な私(小学生の時、左耳の中耳炎をこじらせた後遺症か、気圧が変わると耳が激痛に襲われる)は、その上、最近は警備の強化で刀を持っていると搭乗に時間がかかる事もあって、専ら地上を移動している。そのため、明日昼前に現地に着かねばならないので、今夕"のぞみ"で博多入りする事にして、現にいま博多に向かう車中でこれを書いている。
1時過ぎの"のぞみ"で、朝8時前に起きたのだから、今日は多少余裕をもって家を出られると思ったが、新しい企画の依頼やら問い合わせが相次ぎ、結局いろいろし残したまま、例によってアタフタと家を出る。出る間際、「あっ、財布が・・」と思い、慌ててずっと引き出しに入れておいた家置き用のものを懐に入れる。というのも、約9年間、外出時には常用していた財布が、先日テレビの収録に塩浜へ行った時に紛失してしまったからである。9年間の間、忘れたり落としたりした事は5回はあったと思うが、その都度必ず戻ってきて、「これは失くしても必ず戻る」という妙な確信があったのだが、「今度ばかりはお別れかもしれない」という気持ちが心をよぎった。それというのも、何故かスイカなどのカードを抜いて別の所に持っていたし、現金も3〜4000円ほど入っていただけだった事もあるが、何かどうも私の運気が変わってきたような気がするからである。もし戻ってきてくれれば、もちろん幸いだが、戻ってきたら引退をしてもらって新しいものに換えようと思う。
こんな思いが湧いたのも、昨夜久しぶりにかつて私が大変世話になった畏友N氏と電話で話しをした事もあったと思う。N氏は宗教、なかでもある流れの神道に詳しく、私も随分といろいろなことを教わった。
今日、私が家を出る間際に、電話や手紙で入ってきた3件の新しい企画の依頼はどれも断りがたいもので、特に筑摩書房の橋本治氏が企画提案をされている「ちくまプリマー新書」の企画は、かねてから私が漠然と考えていたものをハッキリとした形にされたような気がして、それだけに、これは大変断りづらい。(まだ時間もあるので、十分検討するつもりだが)
しかし、昨日も1件受けてしまったし、物理的に時間が足りないと思うのだが・・・。
いま、九州での予定を全て終え、曇り空の九州北部を西から東へと移動中。16日に博多入りし、17日、博多ふくふくホールで自然農の実践指導者として知られている川口由一氏と公開対談。第1部と2部を合わせて4時間に及んだが、それ以後の打ち上げ1次会、2次会はそれ以上の刻が消え、全部で約11時間以上多くの人達の前で話をし、体を動かした。ただ、問題意識のある人達が多かったためか話し甲斐もあり、17日の午前零時を過ぎても、まだ余力が残っていた。川口氏は勿論、いろいろお世話になったスタッフの方々、なかでも村山氏、山本女史には心から御礼を申し上げたい。今回は、滅多にない方と長時間お話しをさせて頂いて、一般的な講演会では話した事がないというところまで話が及んだのは、私にとっても得難い体験だった。
翌日は、午前10時過ぎ、佐世保から佐世保の会を世話して下さる平田接骨院の平田院長と村山氏が車で博多まで迎えに来て下さり、直に佐世保に向かう。途中、肥前唐津の"虹の松原"を抜けて行く。全長3キロぐらいはあっただろうか、とにかく右も左も松、松、松・・・。私もある程度全国を廻ってはいるが、これほどの本数の松林は今まで見たことがない。恐らく数十万本は松の木が生えていたように思う。海岸に近いため黒松だと思うが、松にはある特別な思い入れがある私としては思わず高揚する気持ちを抑えきれなかった。この松林を抜けてしばらく行って、又気になる古い社を見つけ、車をわざわざ返してもらい参拝。
ただ、そうした都会を忘れる九州の緑に囲まれたところへも仕事の電話は追いかけてくる。20日の午後までは旅先で比較的ゆっくり出来そうだが、20日、東京に着いたら家に帰るまでに2〜3件寄るところが出来そうである。
18日午後から佐世保武道館での講習会は、また様々なスポーツや格闘技、武道等の方々が集まられ、質問に答えているうち3時間がたちまち経った感じだった。その後は沖縄料理(というか東南アジア系も含む)の店で打ち上げ。ここも前日同様、会そのものより打ち上げの時間の方が長くなってしまった。ただ、熱意ある方が多く、それだけに時間は知らず知らずに経った感じだった。
今回の佐世保の会も平田雄志院長はじめ、村上氏、小川女史、その他にも何人ものスタッフの方々が本当によく助けて下さった。深く感謝の意を表したい。
今夜は大阪で泊まり、例によって名越クリニック院長宅に泊めて頂く予定。名越氏といえば、私は旅先で見ていなかったが、17日夜放映された曙氏出演の「グータン」は相当反響を呼んだようで、名越氏のホームページのアクセスが一気に増えたらしい。なにしろ博多での会の打ち上げの最中、あまりにアクセスが多いので驚いた名越氏から私のところに電話がかかってきた程である。恐らく1日のアクセス件数としては、今月の初め頃に比べて7〜8倍にはなったようだ。
世の中に名が知られるということは、当然厄介なことも増えると思うが、これから降ってくる様々な問題も是非肥料として、更に人間の心の深層に迫る稀有な人物となって頂きたい。
今日20日は毎日放送の角淳一氏と会食してから帰京。東京駅では『文藝春秋』誌の編集者、渡辺女史の出迎えを受けて、先日畑村洋太郎先生と行なった対談のゲラを受け取る。当初はザッと目を通して打ち合わせをして持ち帰るつもりで新宿の"滝沢"に入ったが、打ち合わせをしているうち、〆切と私の予定を考え、この際この場でやる事に決め、本格的な赤入れを始める。校正して増減する字数は渡辺女史に数えてもらい、私の発言分、約四千字をすべて赤入れし、行数をプラス・マイナス・ゼロに調整した。
私一人でなかったから、何とか早く終わらせようと思って凄まじく集中したため、体感的には45分くらいだったが、実際は2時間を越えていた。
「渡辺さん、御苦労さまでした」
これで明日は少し落ち着いて出かけられる。
「3日に一度は、この"随感録"を更新したい」と、つい先日書いたばかりなのに、もうその約束を破ってしまった。ここ数日の間に、いくつもの事が重なり、本当に時々仮眠しながら長い長い1日を送っていたような気がする。
21日はバスケットボールの日本代表選手の1人であるH選手と防衛大学校へ行く。待ち合わせ場所は御徒町の岡安鋼材のナイフ・ショップ。一風変わった場所にしたのは、岡安社長にも会いたいと思った事と、ここで宝島社の田村氏と待ち合わせ、井上雄彦氏との新著『武』(ぶ)の見本本と表紙絵の色見本を受け取る約束をしたからである。
岡安鋼材でも防大での道中でも、いくつも面白いことがあったが、それらを書いていると、とても時間がないので、防大の体育館では又いくつか気づきがあった事を少し書くにとどめたい。その中の1つは、足裏の垂直離陸はもちろんだが、足裏水平にしての垂直落下の重要性もあらためて気づき、中国武術で「平起平落」と、これらを1セットにしている意味があらためて分かった。
22日は留守中の山のような用件に追い回されるが達成目標の10分の1も片づかない。『武』の見本本を特に世話になった人に送ろうとしたが、その発送もこの日は2冊のみ。多くの用件が最優先の順番争いをして頭が割れそうだ。
『武』に関しては、腰帯の「本当の武士道がわかる本」には参った。「正しい」とか「本当の」という言葉を発するのは、きわめて後ろめたい私の本に、出版社が"あおり"で付けたとはいえ、人に送るのにきわめて気が進まない。せめて、「武士道の新しい解釈」にして欲しかった。(しかし出てしまった以上、仕方がないが・・)
23日も24日も、25日も26日も片づかないまま人が来て、話をしたり稽古したり校正したり…。
ただ、足裏の垂直落下は、確かに新しく又動きを開きつつある。鍔競りになりそうなところの斬り割り、斬り落とし、突きの迎撃、体当たり等が変わってきた。
ここ数日で、又いくつか新たな用件を引き受けたような気もするが、メモを取る暇もないような生活の中で、私に用件を依頼された方は、必ず再度、再再度、確認の御連絡を頂きたい。
そういえば昨日、「世の中ガブッと」(テレビ東京夕方6時30分から)で介護の実演を行なったのだが、この収録時に気づいた全介護状態の人を椅子から立ち上がらせる技は、私個人的には最も観たかったのだが、放映されず残念だった。
この番組も放映前に告知しようと思っていたのだが、あまりにもやることが多く、ついつい告知し忘れてしまった。見逃された方には申し訳なかった。次回介護の実演をする時は告知を忘れないように努力します。
今日も嬉しくもありがたくもあり、それだけについ見入って仕事の手が止まるものがいくつか届く。その中でも『続・剣の精神誌』執筆のための資料集めと基礎研究を進めてもらっている宇田川氏からの調査報告は、その労作ぶりにタメ息が出るほど。
一昨年暮れ、かの無住心剣術三代目真里谷円四郎の子孫の方を探し当てた探究力にも兜をぬいだが、今回の資料にも感嘆せざるを得ない。天真一刀流開祖・寺田五右衛門(五郎右衛門は誤り)宗有の、今まで聞いたこともないエピソードなど、つい読んでしまう。この労作に報いるためにも本は書かねばならないのだが・・・。
あと、『世の中ガブッと』の私の介護術に関しての感想が、群大の清水宣明先生と収録時、介護についての現状を説明してもらった介護の専門家、岡田慎一郎氏からFAXや手紙が届く。私の方法を取り入れている岡田氏によれば、「甲野先生の方法は、現場ではとても有効なのですが、あまりにも今までの介護の方法と違うので反発もあるようです」との事。例えば、「武術なんて人を傷つける技からの応用は、福祉の心がないから良くない」という反応もあるらしい。(そんな事を言い出したら、今ごく普通に多くの人たちが使っている通信技術や乗り物は軍事目的で発達してきたものからの応用が少なくないと思うのだが、このような意見を言う人はそれらを使う事も良くないのだろうか。)日本の武術は活殺両面があり、柔術家が療術師でもあったという歴史もある。もう少し心を開いてもらいたいものだ。
そうこうしていると、昼過ぎに中国滞在中の光岡師から電話。今回は久しぶりに韓星橋老師と会うことが出来、ちょうど同行していた日本から現地に学びに行っていた私も良く知っている四国の守氏をはじめ何人かの人達も面会が叶ったとの事。
韓星橋老師は100歳近い高齢ながら実際に動いて下さったらしい。そして、その瞬間、場の空気が一瞬にして変わったらしい。その話を聞いていて、その場にいた人達の感動が電話ごしに伝わってくるようだった。それはそうだろう。かの意拳の開祖・王向斎老師の許に来客時、「これが意拳の動き」という事で拳舞を舞う事を許された唯一の人であり、数多い王向斎門下でも特別の存在であった人を、現に生身で目の前にしたら、この世界に思い入れのある人であれば感動しない方がおかしいだろうから。
最後にインフォメーションです。
漫画家、井上雄彦氏との対談という形でまとめた『武』(宝島社刊)が全国的に発売されました。本の後半では、私の思っていた事がかなり言葉になったと思います。価格は税込1260円。初版一刷は全国に配送され、版元には皆無との事です。連休明けまで増刷体勢には入れませんので品切れとなる可能性があります。(なにしろ井上氏の知名度は群を抜いていますから)購読ご希望の方はお早めに書店へいらして下さい。
昨日は、ここ数日間もっとも気にかかっていた岩波書店から依頼されていた、雑誌『科学』の原稿を書く。約4000字のうち1000字くらいは書いてあったのだが、残り3000字を1時間半ほどの間に滅多にないほど集中して書く。そのため、その集中のピークにかかってきた電話には、生返事で殆ど喋らずに対応していたような記憶が微かにある。
お蔭で夕方からの田町の講座に間に合う時間に終わり、「今日はちょっと(といっても10分ぐらい)余裕があるかな」と思ったのだが、FAXの調子が悪く、それを何とか直したら冷凍品の配送。あいにく、ちょうど家人が皆出払っていた時で、その場に放って家を出る訳にもいかず、結局予定の電車を1本乗り過ごし、また例によってアタフタと田町に向かった。
田町では技を実演解説していて、又いくつか気づきがあった。特に相手が両手で突き放してくるのを、こちらが手を使わず体幹で受け返す時、ある1点にタイミングを合わせると、相手がフェイントをかけた時などすかされてしまうが、準備をしない力(つまり常に準備が出来ている)は、こうした事に左右されず出来るのだという事をあらためて実感した。その機能を上げるため、今は足裏の垂直落下を手がかりにしている。
やはり武術というのは命がかかっていただけに、一般の体育理論では不可能と思われる事も追求していたのだという事を最近あらためて感じているが、この準備しない力もその1つだ。
ただ、それにしてもやる事の多いのには参る。私の記事に載せるとの事で依頼された写真の選定、梱包、そして、その発送、書類の整理、片付けようと思えば思うほど、益々畳が見えなくなるほど書類が拡がる。今、「本業は何ですか?」と誰かに聞かれたら、思わず「雑用です」と答えてしまいそうだ。
その上、朝吹女史から『土佐打刃物』などという本が届いたから、ついつい見てしまい、今日もたちまち日は暮れた。