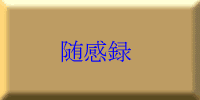 |
2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2001年 2005年 2009年 2013年 2002年 2006年 2010年 2014年 2003年 2007年 2011年 2016年 2004年 2008年 2012年 |
私がいま、ここに転載する7日のツイートと、このツイートの最後に紹介した、森田真生氏の―懐庵便り―を御覧下さい。
日本列島は次第に春の陽気に包まれてきた。そして、この陽気は放射能も広く拡散するという事らしい。しかも、それを止める方法はない。という事は、好むと好まざるとにかかわらず放射能を浴びるということだ。
私はずっと昔から原発の存在をいいとは思わなかったし、むろん放射能浴が好きというわけではないが、事実として舞っているというものを息をつめて避けるわけにもいかない。となれば、その現状を受け入れるしかない。
別に政府の肩を持つわけではないが、事ここに至って「いつになったら安全と言えるのか」という質問に答えろと迫っても、それは誰にも答えられないだろう。何しろトラブル直後、「チェルノブイリなどとはまったく違って安全に停止しているのですから」と専門家が答えていたのだから。
本来、事故というのは想定外のことが起こるから事故というのだろう。
ただ、昔は戦争や事故が起きて悲惨なことが山ほどあっても、放っておけば元に戻った。だからこそ「国破れて山河あり…」という詩も生まれた。しかし、原発とプラスチックを発明・実用化して以後、誤りを犯す人間が、その誤りを犯す意識を使って管理しなければならなくなったのだ。
「そもそも、それが大間違いだ」と、二十代の頃は私の中の何かが怒り狂って叫び続け、いまなお、それは私の心の中に大きく在り続けてはいる。
その怒りは、いまなお、それこそ核燃料のように、冷やしても冷やしても容易に冷めることなく数十年在り続けているが、その一方で「人間の運命は完璧に決まっていて、同時に完璧に自由」という私の人生の根本を貫いている気づきを得たのも二十代の初めだった。
そして、その時思った。「例えどんなに金銭を持つようになろうと、どれほどの権力を持とうと、凄まじい事故、天変地異に巻き込まれれば、そんなものは役に立たない」
「その時、役に立つのは自分が人として生きている、あるいは生きた、という事を体感・実感を通して納得する事だ。いま人生の幕を閉じる時が来たのであれば、それはそれで納得してそこで幕を下ろしたい」と。
だからこそ、この、理論としては、私のなかで、もはや決して揺らぐことがない「人間の運命が完璧に決まっていて、同時に自由だ」という事の二重性を追求することを「人生の目標にしよう」と決め、その事が一番端的に追求できそうだと思って武の道に入ったのである。
そして今回、そのあり得べからざる非常事態が来た。
いま首都にいる我々は、現実に凄まじい勢いで迫ってきた津波の恐ろしさなど、命からがらの切実さを味わってはいないが、「明日は我が身!」今後何が起こるか分からない恐れを多くの人が抱いていると思う。
また、突然の変事ではなくても、真綿で首を絞められるように、次第にいままでとは違った生き方をしなければならない事実を突きつけられるようになることも感じ始めていると思う。
このような時こそ、何が大事なのか、自分にとって生きて在るという事は何なのかを、厳しく問わなければならないと思う。
そういう意味で、私は自分が武術という事の追求に自分の一生をかけてきた事は、私としては正解だったと、いま、今までで最も鮮明に思うことが出来る。
そして、これは人間としては幸せな事だと率直に思う。
もっとも、この幸せ感というのは、いい湯加減の風呂に入って感じる幸せ感では無論ない。記憶をたどれば、弘前で、初めて真剣どうしを打ち合わせて、2、3メートルも火花が散った時に感じた緊迫した充実感に近いだろうか。
今回の原発トラブルで、私の中も相当に揺れた。社会的な事故や事件で、あれほど自分の心が揺れた事は、かつて一度もなかった。そして、この事故は、いまなお予断を許さないが、私はどうやら3月11日以後で、今日が最も我に返ったように思う。
これは多分、昨日震災以来初めて本格的な一人稽古をしたからだと思う。そして武術に志した32年前の思いが蘇ってきたのだろう。
何しろ私は、今から32年前、松聲館道場を建て、武術稽古研究会を立ち上げた時、武術とは何かという問いに対して「矛盾を矛盾のまま、矛盾なく取り扱う」という事と、「人間にとって切実な問題を最も端的に取り扱うもの」という答えを用意していた。
前者は「人間の運命は完璧に決まっていて、同時に完璧に自由である」という私の気づきを、武術の「術」という世界に展開して得られるであろう究極の答えである。
そして後者は、スポーツとは根本的に異なって、人が決めたルールがない状態を扱う武術が本来的に持っているものである。
この30年以上前に言っていた事が、まさに試されようとしている。
私がこのように自らの志を再確認した時に符節を合わせたわけでもないだろうが、私と『この日の学校』を共に立ち上げて講師を務めている数学者の森田真生氏が、「懐庵便り」を創刊し、その原稿が昨夜遅くに届いた。
人間というものの存在を原生動物の発生から続く命の歴史を通して考察したユニークな論考で、これはまた人間というものの在りようを根本的に考察したものなので、氏の許可を得て私のサイトの「随感録」で紹介しておきたいと思う。
懐庵便り - Thinking Being(「思う」存在)として生きる
人として生きる、ということ
幸か不幸か、私も、この文章を前にしているあなたも、ヒトとしてこの世に生まれてきた。
世界を見回してみると、石ころがあれば、太陽があり、ミミズもいれば、楓の樹もある。
人として生きるとは、どういうことだろうか。
もとを正せば、石ころも、太陽も、ミミズも楓の樹も、私たちも、みな同じ場所から生まれてきたはずである。それが、長いながい宇宙の歴史のなかで、それぞれがそれぞれの時間を背負い、それぞれがそれぞれの存在の形式を獲得してきた。
私たちの遠い祖先は、およそ40億年前の地球の海のなかで、はじめて「自己複製」ということを始めた特殊な高分子(=核酸)であると言われている。物質のみからなる原始地球上で、これらの高分子はそれぞれ個性(独自の塩基配列)を持つという意味で、それまでにない、新しい存在の形式となった。
個性を持ち、その個性を自己複製によって継承していく方法を編み出したこれらの高分子たちは、あるとき、おそらくはなんらかの偶然により、自己複製のための素材やエネルギーを囲い込むための「膜」を作り出すようになった。こうして、地球上はじめての「細胞」が誕生し、同時に、地球上ではじめて「内側」と「外側」を区別する存在が出現したことになる。
ここで生命40億年の歴史を振り返るつもりはない。とにかく、その後も私たちの祖先は、途方もない時間をかけて紆余曲折を経ながら、決して平坦ではなかったであろう進化の道程を辿ってきた。その過去から連綿と続く「生命の記憶」として、私たちはここに存在しているのである。
生命40億年の歴史のなかで、心の歴史がせいぜい数千年とするならば、いきいきと全身を協調させて動きまわるゾウリムシやアメーバなどの単細胞生物に比べて、私たちヒトが、あれこれといつまでも思い悩んだり、「あたま」と「からだ」がちぐはぐでなかなか統率がとれないのも、ある面では仕方がないように思える。
「おのずから」と「みずから」のあいだで
「自」という字は日本語で「おのずから」とも「みずから」とも読む。これは一見して異なる二つの日本語に、同じ「自」という字を当てようという古代日本人の配慮があったことを意味している。その背後には、どのような考えがあったのだろうか。
大野晋氏によると「おのずから」と「みずから」に共通している「から」は、国柄や山柄の「柄」であって「おのずから(=己の柄)」「みずから(=身の柄)」であるという。
だとすると、この「自」という字の中には、こころを持つ存在として生きる私たちの困難が端的に表されていると言えるのではないか。
私たちは、常に「生かされている(=おのずから)」と同時に「生きている(=みずから)」存在である。「自」という一字の中に「みずから」と「おのずから」の両側面が共存しているように、私たちもまた、私たち自身のうちに「みずから」と「おのずから」の双極を抱えて生きている。
ヒトとして生きること、あるいは心を持つ存在として生きることの困難は、同じ個体に共存しているこの「おのずから」と「みずから」の双極と、そのあいだの葛藤ということに集約されるのではなかろうか。
私たちは、ヒトとして存在しはじめたその瞬間から、相矛盾するこの二つの傾向のあいだを引き裂かれそうになりながら、そのあいだに立つものとして生きることを余儀なくされているのである。
「思う」存在
独自の視点から人体の発生学を追究した三木成夫氏は、ヒトの中に共存している「動物的」と「植物的」の二つの方向を強調した。
こうしてみると、先の「おのずから」と「みずから」の葛藤は、人の中の動物的(=みずから)と植物的(=おのずから)の葛藤として、すでに人体の発生の最初期から、身体の形態の中に刻み込まれているということになる。
さらに、人の中の動物的側面を象徴するのが、外胚葉から分化して大きく発達を遂げる人の神経系(=脳)であり、一方で人の植物的側面を象徴するのが、内胚葉から分化した内臓系の中心に位置する心臓であると考えると、「おのずから」と「みずから」の葛藤は、「神経系(=脳)」と「内臓系(=心臓)」の葛藤として象徴的に身体そのものに刻印されていると見ることもできるが、実はその様子は図らずも「思」という一字の中に集約されている。
というのも「思」という字は、その上半分が脳を上から眺めたところを、その下半分が心臓のかたちを表していて、脳に偏るでもなく、内臓に偏るでもなく、「あたま」と「こころ」が互いに寄り添って存在している様を表していると言われているのだ。己のうちに「みずから(=動物的)」と「おのずから(=植物的)」とを抱えながら、そのどちらに寄るでもなく、両者が互いに寄り添って存在していることを指して「思う」というのである。
「思う」場所としての懐庵
人の存在の特異性は、同じ個体の中に相矛盾する双極(みずから-おのずから、動物的-植物的、神経系-内臓系)が共存していることであって、人として生きることの困難は、この双極のいずれの一方にも偏ることなく、いかに両者の「あいだ」に立って生きるか、ということにあるのだろう。
懐庵は「思う」場所である。
私は大学で数学を学び、日々教室のなかで数学を「考える」ということをしてきた。
しかし、その点が大学での研究活動において強調されることは少ない。
本来は身体や環境を総動員した行為であるはずの数学も、大学においては、まるで脳と紙と鉛筆の小さなループの中で完結した行為であるかのように扱われている。
私が糸島という場所に「懐庵」という数学の新しい研究所をたち上げたのは、「思う数学」というのを真剣に追求したいからだ。「あたま」に寄るでもなく、「からだ」に寄るでもなく、その両者を総動員した「行為としての数学」というものをつくりだしてみたい。
そのために、数学を脳と紙と鉛筆の小さなループから解放し、環境と身体を動員した"thinking"ということを、様々な方法で実験したいと考えている。身体を使って数学をするとはどういうことか、環境を動員して数学をするとはどういうことかを、あらゆる角度から模索してみる必要がある。
私は、かつて数学が「発明」されたのと同様に、いずれまだ私たちが知らない新しい「行為としての数学」が発明されなければならないと思っている。
この「懐庵便り」では、その新しい「行為としての数学」の発明に向けて、私が考えていることや研究していることを整理して言語化すると同時、今後「懐庵」でどのようなたくらみを実現していきたいと考えているかを具体的に発表していきたいと考えている。
心を獲得して数千年、私たちはまだ、真のThinking Being(「思う」存在)へと向かう道を出発したばかりなのだろう。皆さまとともにここで、未来へと続く「人として生きる道」の、最初の小さな芽を見出し育てていけたらと思っている。
この世の中には様々な存在の形式があるが、その中でも私たちは「ヒト」という特異な形式で「いま、ここ」に存在している。
中でも私たちヒトは、同じく太古から連綿と続く記憶を背負うその他の地球上の生きものたちにはなかった「心」を持つ存在として、他の生命がそれまで経験したことのない、未知の生を生きはじめるようになった。私たちが「心」を持つようになったのは、ここ数千年くらいのことであろうと言われている。
私たちは、心を持つようになってからまだあまりにも日が浅いのだ。
したがって「おのずから」も「みずから」も、ともに「自己の柄(=自分自身に起源をもつ本性)」を意味する日本語で、その「己」の側面に寄るのと「身」の側面に寄るのとで、ふたつの表現が使い分けられていたと考えられるのである。
これは「こころ」を通して「生かされている自分」を意識し、その意識に基づいて次の生き方を「みずから」考えることができるようになった人になって、はじめて抱え込むようになった双極である。
ヒトの発生を、原腸胚形成まで遡ってみたときに、原腸胚は腸腔を抱え込むかたちで、やがて筋肉や神経系に発達していく「外胚葉」と、消化器系に発達していく「内胚葉」に分化していくが、三木氏は、この外胚葉と内胚葉の分化のうちに、ヒトの中の動物的(=外胚葉)と植物的(=内胚葉)の共存を見た。
数学を「考える」ということは、決して脳内で完結したプロセスではなくて、少なくとも紙と鉛筆と脳の相互作用のなかで進行する過程であるし、もっと言えば身体の状態や環境のありようも深く関与してくるような、環境に開かれた行為である。
それはたしかに、人の中の「みずからとおのずから」、「動物的と植物的」を総動員した、真の意味で「人らしい」行為である。
その証拠に、大学の教室はどこも同じような形状と色合いであるし、授業を受ける身体の姿勢や、机に向かう姿勢そのものを改良しようとすることは普通はしない。
以上1日分/掲載日 平成23年4月7日(木)