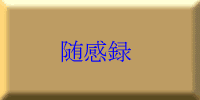 |
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2001年 2005年 2009年 2013年 2002年 2006年 2010年 2014年 2003年 2007年 2011年 2016年 2004年 2008年 2012年 |
5日は久しぶりに仙台での稽古会。そして6日は仙台から水沢江刺駅まで"はやて"に乗って、奥州市立南都田中学校へ朝日新聞の出前授業、オーサービジッドのために出向する。
今回は3年B組と2年A組から、全く別々に朝日新聞に応募があったのだが、決まった時点でどちらかのクラスだけという訳にもいかないと思い、2クラス合同を私から提案したが、この中学校は2年3年共に2クラスずつということで、結局4クラス合同、約100人対象の出前授業となる。それでも話を聴く時は、本当にしんとして聞いてもらえたし、体験にはいくつもの驚きや笑いの輪ができて1時間半はたちまち過ぎた。
終って、校長室から外を見ると、生徒達が竹ボウキで庭を掃いている。そのホウキの持ち方もなかなか板についていたので、ついお節介に、更に有効な方法を教えに行ってしまった。こうした体験をして育つことの重要さを最近はあらためて感じる。
対象が中学生だったので、現代の科学的トレーニングの問題点についてはあまり触れなかったが、それでも話しの流れ上、まったく触れないわけにはいかないので、若い人達がこれから自分の頭と自分の感覚でしっかりと道を拓いていってもらいたいというような事は言ったと思う。
しかし、私に縁が出来、人生が激変した人は何人かいるが、スポーツや身体技法で私の体の使い方に深い影響を受け、あらためて自分で考え、体感で納得した人は、現段階ではまだ茨の道を歩まざるを得ないようだ。どうもそのことが最近なぜか顕著。ラグビーのH選手、野球のK選手等々、そうした人達が岐路に立った胸の内を知るだけに頑張ってもらいたいと思うと同時に、私の30年来の武の道の同志であり先輩であり、畏友である伊藤峯夫氏の言葉、「甲野さんは、まわりをおかしくする変な才能があるから、気をつけないとダメですよ…」を思い出す。この言葉を聞いたのは、もう25年くらいは前だったと思うが、現実に次々と私に縁が出来たことで、私に会わなければおよそ違う道を歩んでいただろう人を見せつけられると、なんとも言えない気分になる。
それにつけても思い出されるのはシナジェティクス研究所の梶川泰司所長から聞いたライト兄弟に対する当時の権威者の論難である。現に飛行機を作ってプロペラを回して飛んでみせても、約1年間くらいは「あれは飛んだのではなく、ただ風に飛ばされていたのだ」という批難が続いたという。
新しいこと(古武術だから新しいということもおかしいが、現行の方法を改革するという点では新しい)を始めると、常に旧勢力からの抵抗があるものだが、知った者、実感を得た者にとっては、その歩みを止めることは出来ないのである。
この先、茨の道を承知で、勇気をもって現状を切り拓いていこうという若い人達が出ることを期待したい。そして、もし志をもって新しい道を拓くなら、受験のための勉強ではなく、新しい時代を拓くため、反対し抵抗し現状を維持しようとしている人々の目を覚まし説得するだけの論理と技を展開出来るようにするために学んで欲しいと思う。
現在の"いじめ"等に対する学校や教育委員会の無力さを見れば、実質的には明治から始まった現行のような教育制度は既に崩壊し始めていることは明らかであり、本当に自分の頭で考え、自分の感覚で道を拓く人物を時代は渇望しているのだと思う。
以上1日分/掲載日 平成18年11月7日(火)
今回は、かつてない週の前半に3回も立て続けにテレビに出るという経験をしたが、今日8日、最後になったTBSの「はなまるマーケット」では完全にテレビの「取り敢えず時間を埋めておけばいい」という姿勢に乗ってしまったことを後悔するハメになってしまった。こんな事なら出るのではなかったと思ったが後の祭り。私も深く反省した。たとえば、岡江久美子さんが試みた「上体起こし」など、初めて取り組む人が陥りがちな典型的なダメな例が修正されないまま放映されてしまい、あわただしく終ってしまった。
当初スタジオで、生でやる予定だったので、それならば、その場で修正も利いたのだが、それが録画に変わり、体験に来館された女優の水野真紀さんが感覚のいい人で、予想より遥かに呑み込みがよかったので、私も油断してしまったのである。今にして思えば、それが逆に仇になった。いかに呑み込みがよくても、ただ一度の体験で他人に教えるには無理がある。上体起こしに挑戦した岡江久美子さんが、どうみても起こすのが楽そうではなかったのは、まず足を置く位置が低すぎる。本来は肩の近くに置くべきなのに脇腹の辺りだった。これでは後ろに体を倒せない。また、手を"折れ紅葉"にして腕が使えないようにしていない等、最も基本的な体勢が出来ていないのだから出来るはずがないのである。
このようないい加減な仕事を私が請け負ったことになるのは本意ではないのでギャラは受け取らないことにした。まあ、とにかく、こうしたことが起こるのでテレビ出演はよほどの例外を除いて、当分断ろうと思っている。もっとも、テレビ出演は長い間、基本的には出ないことにしていたのだが、介護の悲惨な現場の話を聞き、少しはそういう人達の参考になればと思って、いつとはなしに受けてしまったのだが、逆効果では出る意味がない。
本の企画も、今日また1冊話が具体的になってきて、それだけでも手一杯なので、当分、仕事は書くことと講座、講習会など以外は、しばらく遠慮させてもらうことにする。
そうこうしているうちにフランス行きが目前に迫ってきた。
11日から約2週間、日本にはいませんので、この間、私宛ての手紙、電話、ファックス、メール、宅配便等はお控え頂くようお願い致します。
以上1日分/掲載日 平成18年11月8日(水)
池袋コミュニティカレッジの講座の後すぐに成田空港に向い、空港のホテルで一泊し、翌朝JALでパリに発つ。幸いすいていたため、同行の陽紀と三席を二人で使い窮屈な思いをしなくてすんだ。
その上、ダンサーの山田うん女史からのアドバイスに従って、少しづつ絶えず水を飲み非常口の前の空間でしばしば体を動かしていたから、予想していたより遙かに楽だった。
もっとも、今回のパリ行きは、前日になってもまるで実感が湧かず、池袋の講座を終えたら、うっかりするとそのまま家に帰ってしまうのではないかという気がしたほどであった。
一夜を明かして、朝目が覚めて通りを見ても、何か実感が湧かずバーチャルな映像を見ている感じ。そうした感じで通りを眺めて、パトカーの音を聞いていると、三十何年か前のNHK総合テレビで放映されていた奇妙な連続ドラマ『プリズナーNo.6』を思い出した。
とにかく街並のたたずまいは広告がゴテゴテしている日本の都市とは大違いである。
ホテルは今回カロリン・カールソン女史からの依頼に関して、さまざまな世話をしていただいている竹井豊氏にキッチン付きのアパートホテルを借りておいていただいたので、そこで、野菜を茹で、果物の皮をむき、後はパンとチーズとで少しの不自由も感じない。
ダンサー中心のワークショップは明日から開講。さて、どういうことになるのだろうか。
パリに来て四度目の朝を迎えた。
あいかわらず、映画の中に入り込んだような実感のない日々が続く。日本のにいたのが数ヶ月も前のような気がする。あまりに当たり前に時間が過ぎていくが、その当たり前で特別な気がしないということが特別なのかもしれない。あらためて武術とは何かを深く考えさせられている。
それにしても紅葉した木々が美しい。
以上3日分/掲載日 平成18年11月16日(木)
ドイツに入って、もう何日経ったか、それも思い出さぬほど、ただ日々が過ぎていく。ここドイツでは日本武道の道場を構えているR師範に陽紀共々泊めて頂いているが、このR師は道場の代表者であると同時に小使いでもあると言われるだけに、まったく偉ぶるところがなく、多くの人達に慕われているその様子はいい風景である。
この地に来て、一日一日を過ごしつつ、何がどう作用しているのかよくわからないが、こんなにも欲のない自分をみたことがないと驚いている。R師の書棚には私の著作や私が推薦した本がほとんど揃っていたが、その多くの蔵書の中に檀一雄の『夕日と拳銃』をみつけ、ちょうどパリでこの本の事をずいぶん久しぶりに思い出していただけに、不思議な思いに駆られて手にとり所々拾い読みした。読んでみて、その文章や登場人物を驚くほどよく記憶していた自分に、あらためて不思議さを再度噛みしめた。同時に、三十年以上も前に読んだ時とはまったく環境の違う異国で、自らのありあまる情熱の燃やし方に悩みつつも、どうにもならぬ定めに走り続けた主人公伊達麟之助の姿を幕末の傑物の一人、河井継之助などにも重ねて思い起こした。
今回、パリでもドイツでも、異国に来てずっと住みついている何人もの日本人の方々に会ったが、どの方もそれなりに自らのなかから燃え出す情熱と、その方々なりの付き合いをしてこられているのだろう。
ただ日々を過ごすということは、ある面非常に安易だが、同時に非常に難しいということを、今まで感じさせられたことのない深さと微妙さで感じさせられている。
以上1日分/掲載日 平成18年11月22日(水)
24日の午後、約2週間ぶりに日本の土を踏む。日本に帰る前、「また、あのゴミゴミした街並を見なければならないのか」とウンザリしていたが、帰ってくると2週間に近いヨーロッパの旅が、まるで完全な夢であったかのように自分の意識の中では遥か昔の存在になっている。不思議なことに国内を1週間くらい旅行して帰ってきた時よりも、ずっと留守にしていたという違和感がないのである。ヨーロッパにいた時は、日本のゴミゴミとした街並を見て、どんなにか心が塞がれるかと思っていたが、こうも予想が外れると、いったい自分という人間がどういう人間なのか我ながら訳が分からなくなってくる。
ただ、心の中の何かが変わっているらしいことは朧げながら感じられるから、本格的に影響が出るのはこれからかもしれない。
それにしてもドイツのR道場長とパリの竹井豊氏には格別世話になった。ここであらためて御礼を申し上げたい。
以上1日分/掲載日 平成18年11月26日(日)
ヨーロッパに行った影響がどのように私に出たのか、私自身まだよく分かっていないが、ただならぬ影響があったような気がしはじめている。
渡欧してすぐ、フランスでもドイツでも、その、昔からの街並みを受け継ぐことに少なからぬ情熱を注いでいることに比べ、日本のゴチャゴチャした街並みにウンザリして、日本に帰ったらさぞ気持ちが塞ぐだろうと思っていたのに、帰ってみたら突然ヨーロッパは遥か昔の記憶となり、帰宅しても国内を1週間留守にした時よりも変化を感じなかったのだが、驚いたことに『願立剣術物語』や『前集』『中集』といった長年愛読してきた武術の伝書類をどうしても読む気が起こらないのである。
では何を読みたいかというと、『河井継之助傳』といった身の回りの激変のなか、さまざまな葛藤に囲まれて苛烈な生涯を送った人に関するものになぜか目が行くのである。もちろん、どうしてそんな気持ちになったのか理由は全くわからない。ただ、最近の教育現場の荒廃や、あまりにも非常識な親の増殖の報道などを目にするにつけ、足許が崩れていくように日本で生きていこうとする意欲そのものが薄れていく実感もある。
内田樹神戸女学院教授は私との共著『身体を通して時代を読む』のなかで、動物園で自由を奪われて安全に暮らしているシマウマと、サバンナで猛獣から命を狙われる中で生きているシマウマとどちらが幸せかわからないと述べられているが、ただ戦争がないというだけで、何もかも文明の利器にオンブに抱っこで暮らし、周囲に気遣いする感性もなくなった人々と同時代を過ごすのと、生命の危険はあっても、人への気配りや自分の命をかけても自らが守りたいと思うものを守ろうとする気概のある人々と一緒に暮らすのと、どちらがいいかと言われたら、今の私はどうしても後者を選ぶだろう。
「生きている」ということは、本来リスクを伴うものである。そして人は生命以上に大切な何かを持つことで生きることに真剣になれると思う。
最近のいじめによる自殺報道に対して、よく「何よりも生きていることが大切」と安易に言い切ることに、私はどうしても疑問を抱いてしまう。ある人が最近私に、今の日本は何もかも便利になり保護されて、「物語がなくなってしまった」と語られたが、命が最高の価値となれば、それも当然のことだろう。「手術は成功しました。しかし患者は死にました」ではないが、全体のバランスを見ずに、あるものだけを無条件に貴いとすることは、さまざまな問題が生じる。中正不偏ということの真の意味を把握することは本当に難しいことだ。
このように書いてくると、どうやら私の今回のヨーロッパ行きは、何かひどく重いものを私の心の中から引き出してきたような気がしてきた。
それにしてもヨーロッパへ行って講座をしながら、つくづく最近自分のやっていることが大したことではないという感じがしてならなかった。なぜなら、私の技は本当に日常動作の応用であって特別な感じが本当にしないからである。したがって、先般フランスでワークショップをした際、全日程が終った後に、今後私に習いたいので日本に行きたいという人が何人も出た時、正直本当に困惑してしまった。
大したことのない私の技を学ぶ為、ゴミゴミした日本の街並みを見るより、綺麗で落ち着いたパリにいた方が遥かにいいと思うだけに、本当にその申し出を理解出来なかった。
そのためか、27日に綾瀬で、帰国後初めての講座をした時も、確かに私のなかでは今までで一番技が利いているのだが、「それにしても、この程度の稚拙な技を体験するために、わざわざ時間をかけて来て下さったのか」と来場された方々に何か申し訳ない思いが拭えなかった。
以上1日分/掲載日 平成18年11月29日(水)